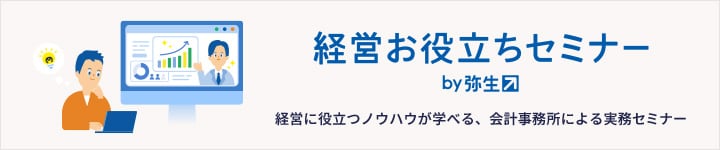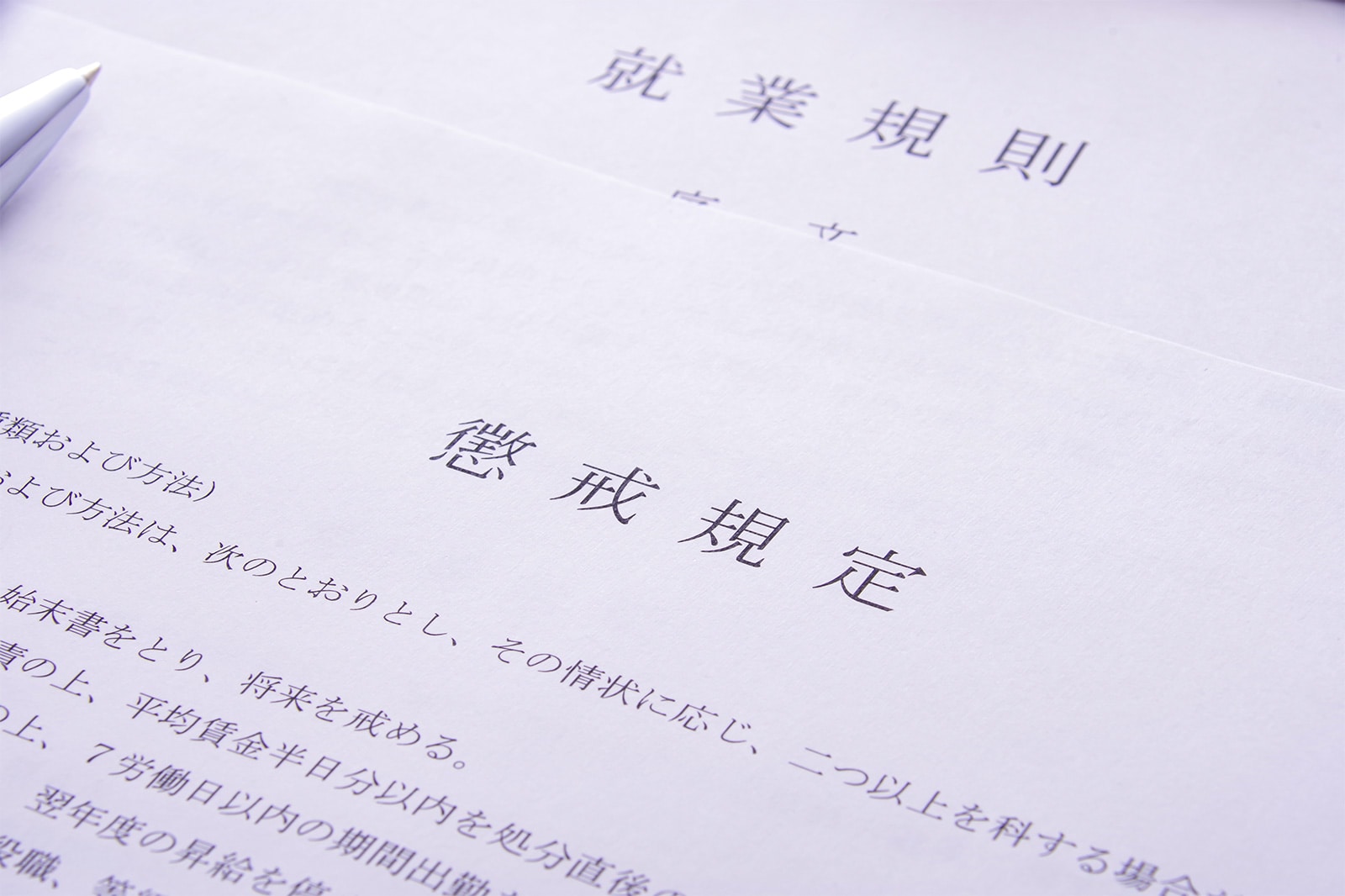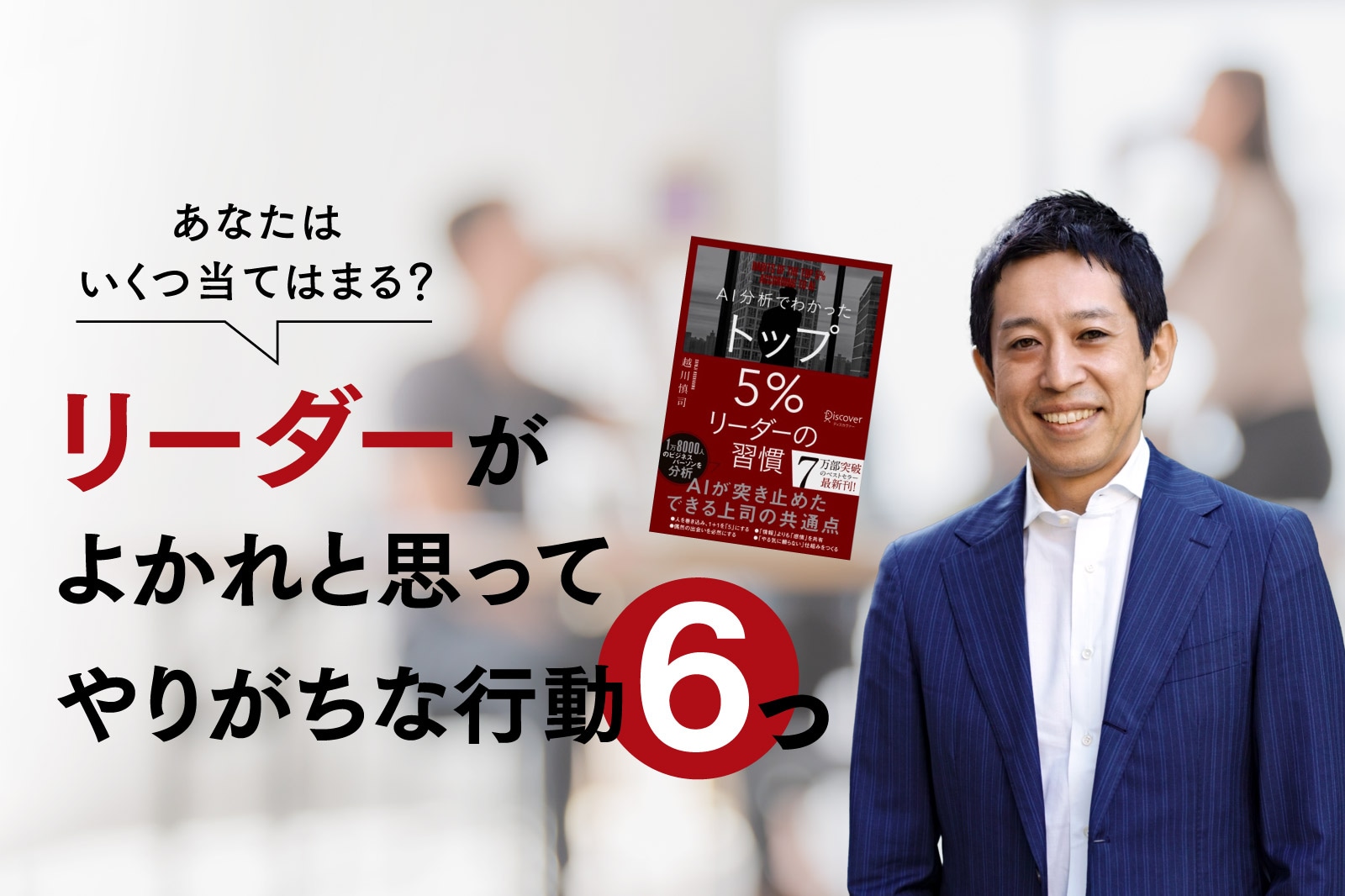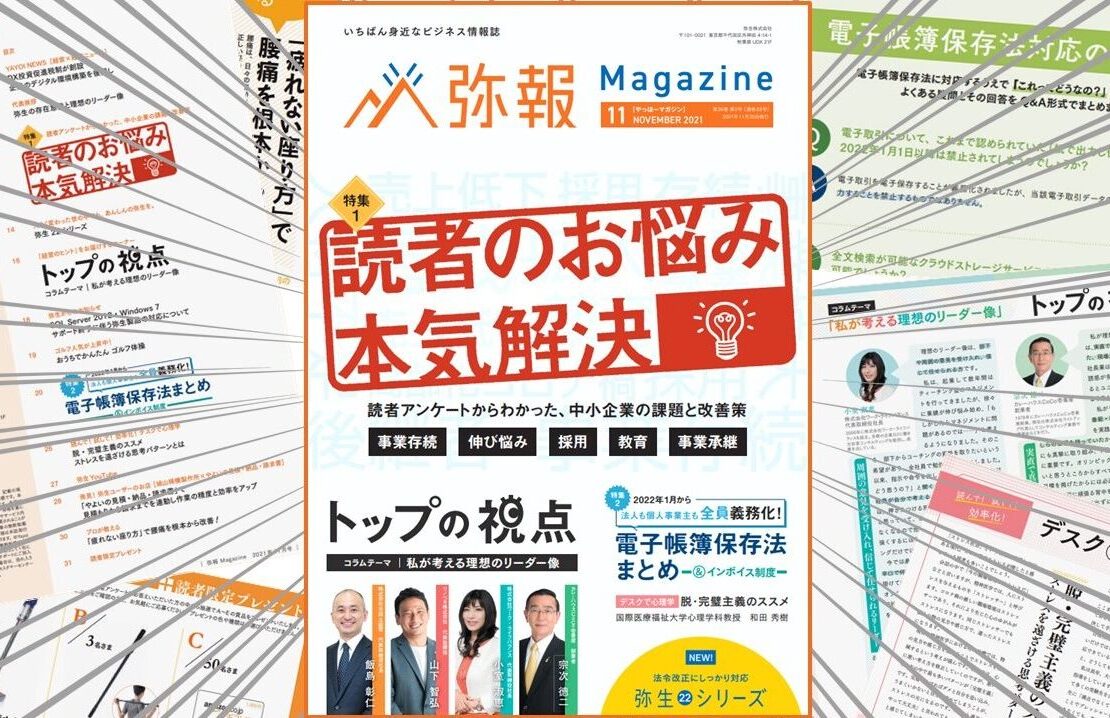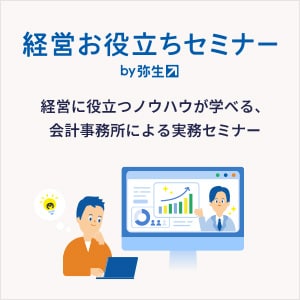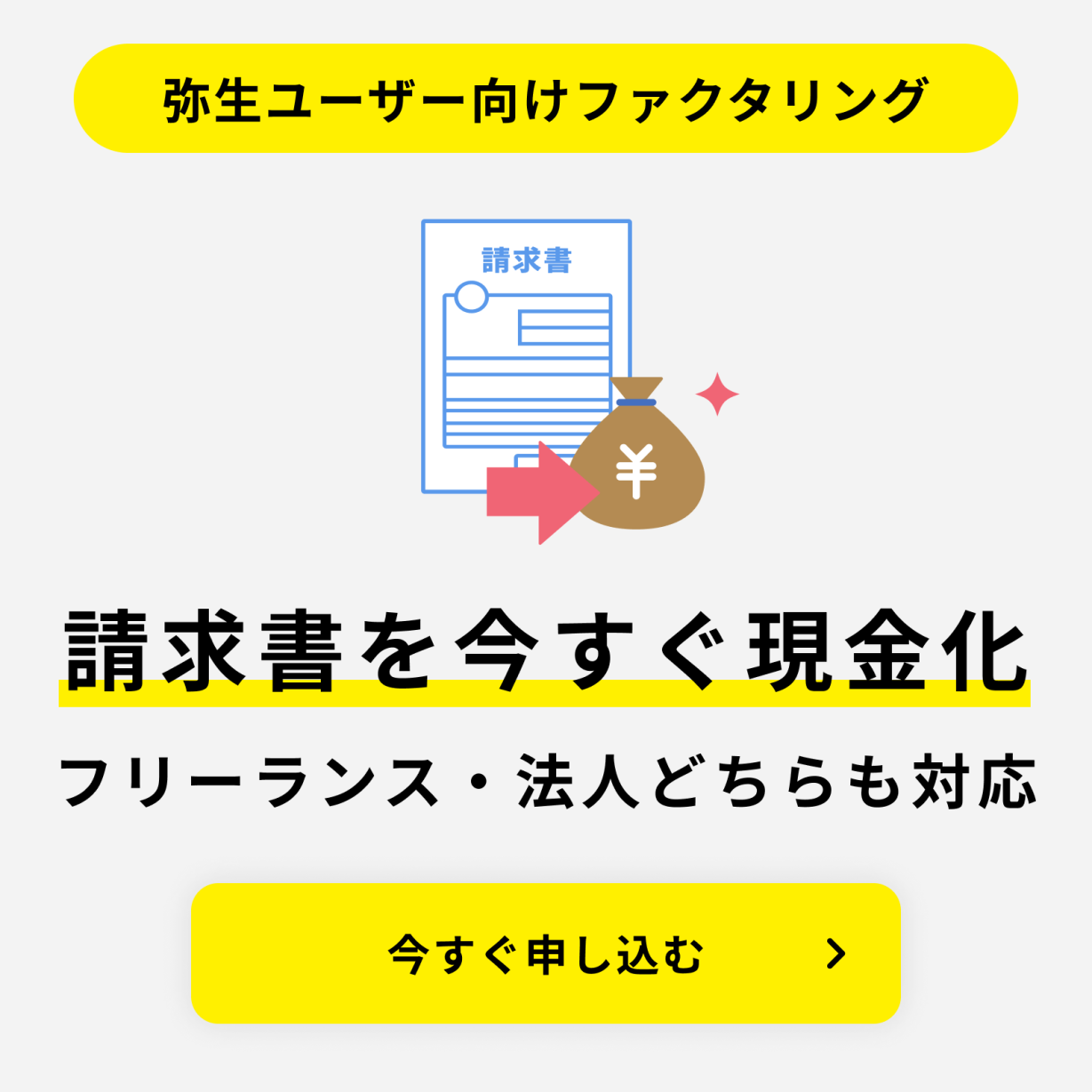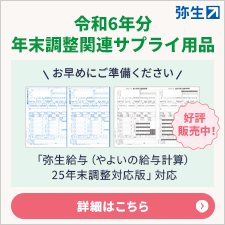- 人材(採用・育成・定着)
採用成功への近道!ハローワークに直接出向いて得られるメリット
2025.08.27

「求人を出しても応募がない」といった声を受けて、ハローワークの活用に消極的な企業も少なくないようです。しかし、今もなお国内最大の求人媒体であるハローワークを活用することは、状況打開の有効な手段の一つになり得ます。特に中小企業にとっては、その機能や各種サービスを上手に活用することで、人材確保の可能性をさらに高めることが期待できます。例えば、単に求人を掲載するだけでなく、ハローワークの「現場」に実際に足を運んでみることが、新たな発見や採用成功への近道になるかもしれません。
今回は、ハローワークを活用した採用支援を専門とするウエルズ社会保険労務士事務所 代表の五十川将史さんに、ハローワークの基本的な役割を押さえつつ、実際に足を運ぶことで得られるメリットや活用のポイントについてご紹介いただきました。
弥報Onlineでは他にも「採用」をテーマにした記事を発信しています。
採用の記事を読む
目次
進化したハローワークの機能と、さらに一歩踏み込んだ使い方
ハローワークは「公共職業安定所」の愛称として広く知られており、「職業紹介」「雇用保険」「雇用対策」の3つの業務を担っています。このうち職業紹介業務では、企業が求人を申し込み、それを求職者に紹介することが基本です。
この機能を補完するのが、ハローワークインターネットサービスです。これは厚生労働省が運営するWebサービスで、企業(求人者)は求人票を掲載でき、求職者はWeb上で求人を検索できます。
2020年1月にはサービス仕様が大幅に改訂され、以下のような新機能が加わりました。
- 求人票フォーマットの刷新による情報量の拡充
- 求人者マイページの開設により、オンラインでの求人申し込みが可能に
- スマートフォンやタブレットによる求人情報の表示対応
さらに2022年3月からは、マイページを通じて求職情報を公開している求職者に対して、企業が直接「応募リクエスト」を送れる機能も加わっています。
このほかにも、オンライン上での求人票の修正・変更、求職者情報の検索、ハローワーク経由の応募者の管理など、多くの機能が利用できるようになっています。これにより、ハローワークインターネットサービスは求人活動の利便性と効率を大幅に高めるツールとなっています。
このサービスの特徴は、求人活動の多くをオンラインで完結できる点にあります。実際、現在では企業による求人申し込みの約9割がオンラインで行われており、ハローワークに直接出向く機会は大きく減少しています。
ただし、オンラインで求人を出せばすぐに応募が来るとは限りません。人手不足が深刻化する中、求人票を出して待つだけでは成果につながらないケースも少なくありません。求職者からの反応や応募を得るためには、もう一歩踏み込んだ工夫が必要です。
例えば、次のような機能を活用することで求職者の関心を引き、応募につなげることができます。
- 求職者に直接アプローチできる「応募リクエスト」機能
- 職場の様子や製品などを伝える「画像情報」の掲載
- 求人票には載らない企業の思いや雰囲気を伝える「事業所からのメッセージ」機能
こうしたプラスαの情報発信を積極的に行うことで、求職者に企業の魅力を伝え、応募を促すことが期待できます。
足を運んでわかる、ハローワークの求人動向と現場のリアル
ハローワークインターネットサービスの機能が充実したことで、近年では採用活動においてハローワークへ直接訪れることはほとんどなくなりましたが、実際に足を運ぶことで得られるメリットもあります。ここでは、あえて「ハローワークに出かけること」でわかる、人材確保のヒントを得る方法やメリットを紹介します。
ハローワークを訪れることで得られる最大のメリットは、現場のリアルな様子を自分の目で見て感じられることです。ハローワークインターネットサービスでは得られない「空気感」や「利用者層の実態」を知ることができます。観察の視点としては、例えば以下のようなものがあります。
1.求人検索用パソコンの利用者を観察する
設置された検索端末をだれがどのように使っているかを見ることで、利用者の傾向が見えてきます。男性・女性の比率、年齢層(若年層・ミドル・シニアなど)、あるいは仕事をしていない期間が長そうな人や、現在も働きながら次を探しているように見える人など、求職者のリアルな一面が見えてきます。利用者の姿から「今どんな人がどんな仕事を探しているのか」のヒントを得ることができます。
2.ミニ面接会の開催状況をチェックする
館内に掲示されているミニ面接会の情報は、今どの業界や職種が積極的に人材を求めているかのバロメーターでもあります。介護、運送、清掃、製造、サービス業など、地域や時期によって傾向が異なるため、ミニ面接会の業種や企業名に注目すると、地元の労働市場の動向や採用ニーズの高まりが見えてきます。
3.掲示されている求人票の傾向を見る
エントランスや掲示板に目立つように掲示されている求人票から、ハローワークが特に注目している業種や求職者ニーズを推察できます。職種、雇用形態、給与水準、勤務地、福利厚生などの情報を眺めることで、現在の求人市場の特徴やトレンド、求職者からの関心の高さ・低さといったことまで読み取れる場合があります。
もちろん、1回の訪問で傾向を判断するのは難しいですが、「現場を見ること」で得られる気づきは、数字やデータだけでは掴みきれない生の情報を得ることができます。今後の求人票作成におけるヒントにつながるでしょう。
求人成功への近道は、「窓口」での直接相談!
ハローワークには、企業側の採用活動を支援するための「求人窓口」と、求職者に求人を紹介する「紹介窓口」があります。一般的に企業は、ハローワークで求人を出す際に求人窓口を利用しますが、求人票の提出後でも、採用に関する相談ができます。訪問にあたって予約は必須ではありませんが、採用戦略の見直しなど、より踏み込んだ相談を希望する場合は、事前に電話で問い合わせておくとスムーズに対応してもらえるでしょう。また、紹介窓口でもさまざまな情報を収集できる場合もあります。いずれも無料で利用できますので、ぜひ訪れてみてください。
1.求人窓口で得られる情報
求人窓口は、企業側の採用活動を支援するための専用窓口で、求人票の作成支援をはじめ、採用戦略の見直しや人材確保に関するさまざまな相談が可能です。単なる窓口対応にとどまらず、地域における採用の「成功・失敗」の傾向を把握しているプロフェッショナルと直接会話ができる場とも言えます。以下のようなデータや助言を得ることができます。
- 募集職種の求人倍率
- 管轄地域における求職者数(性別・年齢層・希望勤務地など)
- 平均賃金・希望賃金の相場
- 新規求人の充足率(地域・職種別)
こうした情報は、ねらう求職者層の絞り込みや、応募につながる労働条件・待遇設定の参考になります。また、日々多数の求人票に接している職員から、応募を呼び込むための具体的な改善アドバイスを受けられるのも、求人窓口に足を運ぶ大きなメリットです。
2.紹介窓口で得られる情報
紹介窓口は、求職者に求人を紹介する業務を担う部署で、企業側にとってはなじみが薄いかもしれません。しかし、こちらでも企業側からの相談やヒアリングを受け付けてもらえる場合もあり、求職者の「今」を知る情報を収集することができます。例えば、次のような内容が得られます。
- 求職者が重視する条件や志向
- 同職種への応募状況や反応
- 労働条件や求人内容に対する要望
- 求人を選ぶときの判断基準
こうした情報は、表には出てこない“現場の感覚”として、今後の求人内容の見直しやアピール方法の工夫に活かすことができます。
さらに、ハローワーク内には対象者ごとの専門窓口・支援コーナーが設けられています。例えば、以下のようなものがあります。
- マザーズコーナー(子育て中の女性向け)
- 中高年専門窓口(ミドル・シニア層の再就職支援)
- 人材確保対策コーナー(医療・介護・建設・運輸など人材不足分野)
これらの専門窓口では、それぞれの対象層に合った情報提供やマッチング支援を行っており、企業側からの相談も受け付けています。また、ハローワークの外部施設として、以下のような若年層向けの支援機関もあります。
- 新卒応援ハローワーク(新卒・既卒3年以内対象)
- わかものハローワーク(おおむね35歳未満のフリーター等対象)
自社の採用ニーズに合った窓口・コーナーを訪れ、最新の情報収集や相談を行うことは、人材確保の可能性を広げるうえで大きな助けとなるでしょう。
動いてつかむ!ハローワーク訪問で広がる採用チャンス
人手不足が深刻さを増す中、多くの企業にとって人材確保はますます厳しい課題となっています。これまでハローワークを利用してこなかった企業にとっても、コストをかけずに利用できるハローワークは、活用の仕方次第でその課題解決に大いに役立ちます。
とはいえ、求人を出して「応募を待つだけ」では、思うような成果につながらないのが現実です。求職者の目に留まり、応募につなげるためには、もう一歩踏み込んだ取り組みが必要です。
本稿は、ハローワークインターネットサービスなどのオンライン機能を活用しつつ、対面による「Face to Face」の支援にも今一度注目し、上手に併用してみようという提案です。
ハローワークに出向くことは、たしかに時間や手間がかかる行動ですが、それによって得られる情報やノウハウは非常に価値のあるものです。うまく活用することで、自社に合った人材を確保するための有効な手段となるはずです。
弥報Onlineでは他にも「採用」をテーマにした記事を発信しています。
採用の記事を読む

この記事の著者
弥報編集部
弥生ユーザーを応援する「いちばん身近なビジネス情報メディア」

この記事の監修者
五十川 将史(ウエルズ社会保険労務士事務所 代表)
1977年、岐阜県生まれ。明治大学卒。大手食品スーパーの店長や民間企業での人事担当者、ハローワーク勤務を経て、独立。ハローワークを活用した採用支援を専門としている。商工会議所、労働局、社会保険労務士会などでの講演実績も多数あり、これまでの受講者は1万人を超える。著書に『中小企業のためのハローワーク採用完全マニュアル』(日本実業出版社)、『ハローワーク採用の絶対法則』(誠文堂新光社)などがある。