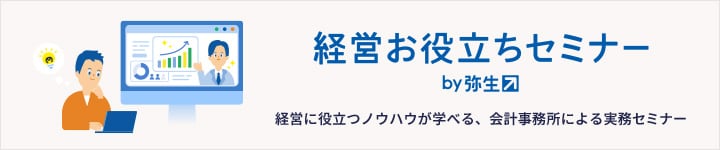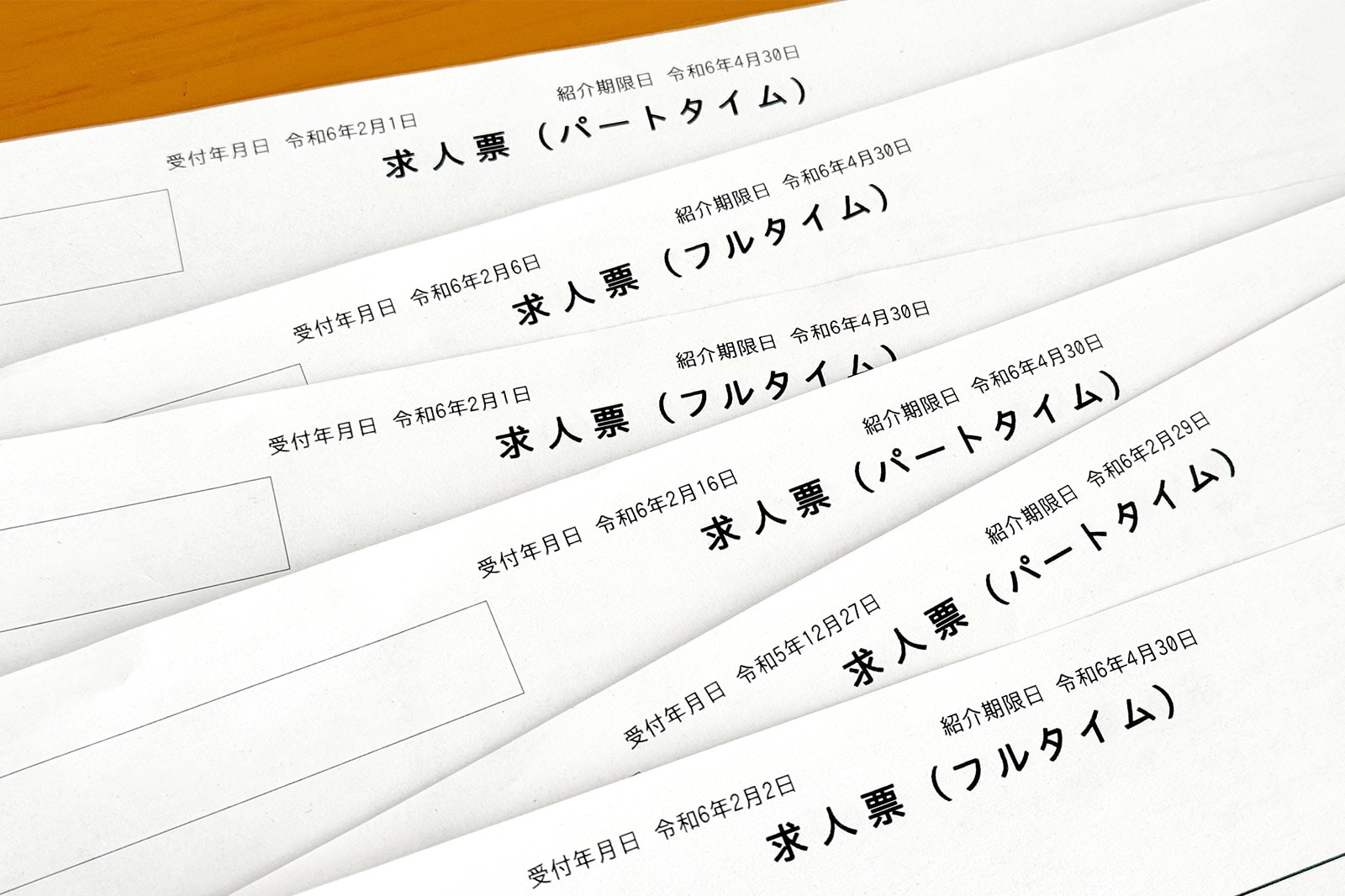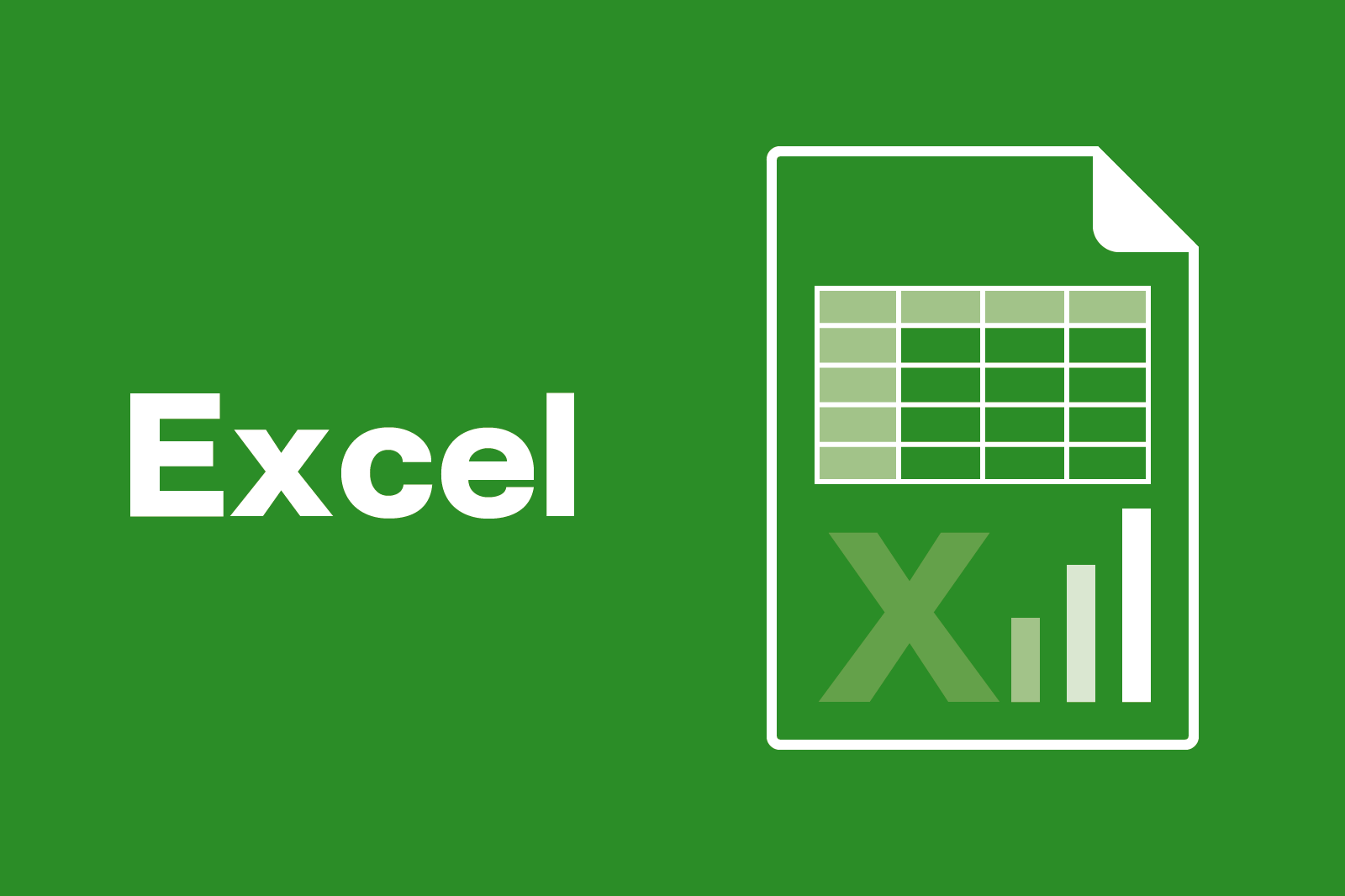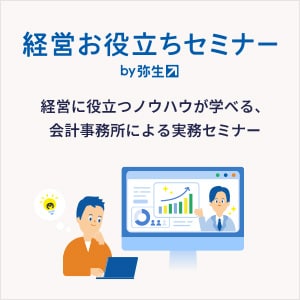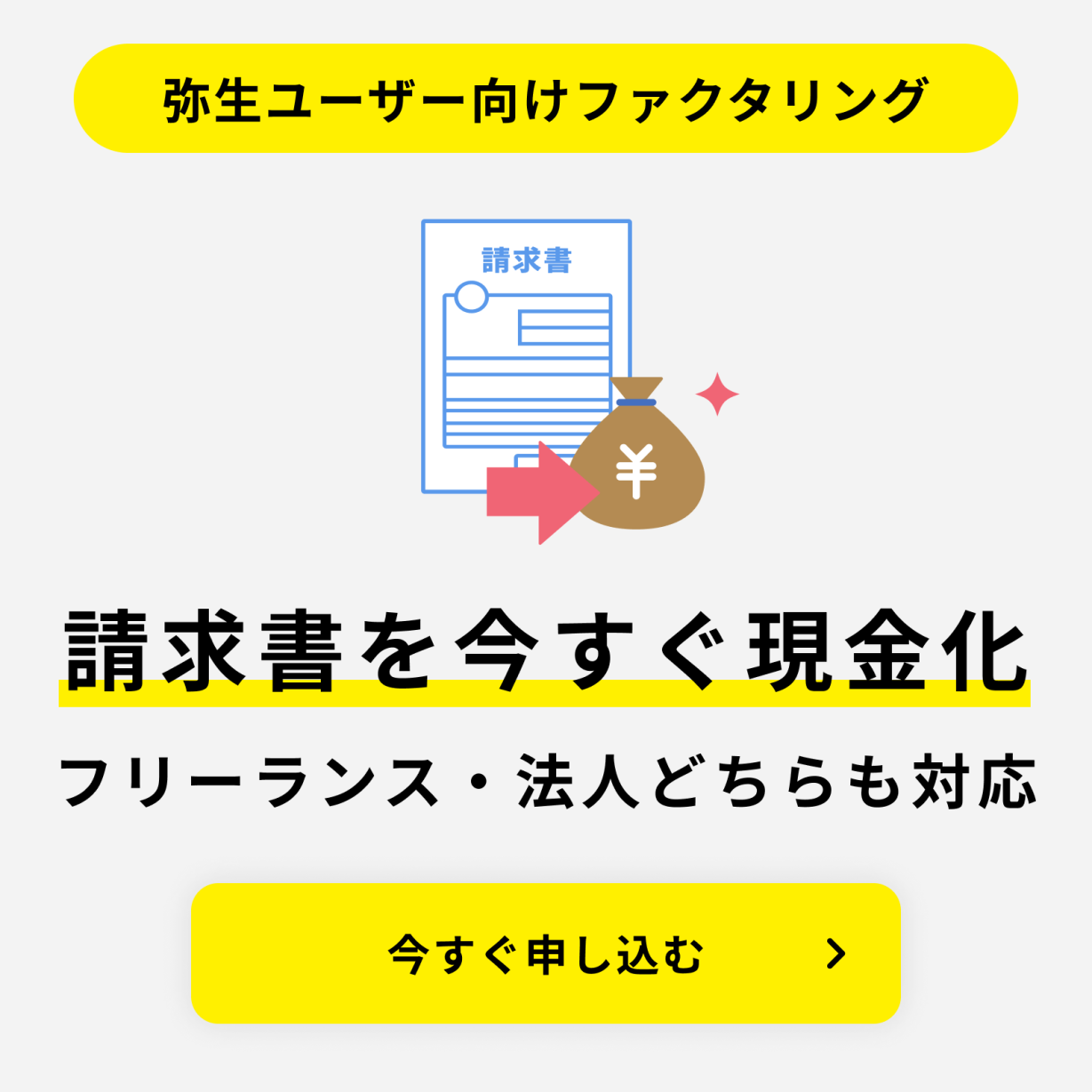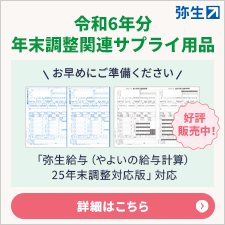- 人材(採用・育成・定着)
面接前の実施が効果的!「会社見学」が採用・定着率アップにおすすめな理由とは?
2025.07.10

企業が会社見学を受け入れる場合、例えばハローワークでは「会社見学歓迎」などの記載を求人票に盛り込み、希望者を募るのが一般的です。特に、福祉や教育業界では、施設の雰囲気や現場の様子が応募の判断に直結するため、会社見学の受け入れを明記する例が多く見られます。
一方で、企業側も会社見学の重要性は理解しているものの、準備や対応に一定の手間がかかるため、多忙な現場では積極的にアピールしづらいと感じる企業も少なくありません。
もちろん、会社見学を実施していないこと自体に問題があるということではありません。しかし、求職者が「実際に自分が働く場所を見てから応募を判断したい」と考えるのは、ごく自然なことです。見学を希望するということは、既にその企業に一定の関心を持っている証でもあり、そのニーズに応えることで、応募へとつながる可能性が高まります。
今回は、ウエルズ社会保険労務士事務所 代表の五十川将史さんに、会社見学がもたらすメリットや、効果的な受け入れのためのポイントについて解説いただきました。
弥報Onlineでは他にも「採用」をテーマにした記事を発信しています。
採用の記事を読む
目次
会社見学は企業イメージに直結する
求職者にとって会社見学を希望することは、転職や就職を真剣に考えている証であり、企業にとっても優秀な人材と出会うための大切な機会となります。応募先の選定にあたって、求職者が重視する条件の一つが「職場環境」です。
特に若年層では、職場の雰囲気や人間関係が、入社後の定着や離職に直結する要因になることも少なくありません。そういった意味でも、会社見学は求職者の不安や疑問を解消し、企業とのマッチング精度を高めるための有効な手段といえます。3つの観点から、会社見学のメリットをお教えします。
1.企業イメージの向上につながる
会社見学の受け入れは、企業イメージに大きな影響を与えます。見学を積極的に受け入れている企業に対して、求職者は「オープンな社風」や「誠実な企業姿勢」といった好印象を抱きやすくなります。
例えば、「ぜひ自分の目で当社の雰囲気を確かめてください」といったメッセージは、求職者に安心感や信頼感を与えることができます。求人票やホームページに掲載されている情報が過度に美化されたものではなく、実際の職場の姿に近いことを確認できる機会を設けることは、企業側が求職者の視点を尊重している証でもあります。こうした姿勢は、企業に対する信頼感を高め、応募への後押しにもつながります。
2.応募前の見学がより効果的
見学の実施は、できるだけ「応募前」に設定するのが効果的です。多くの企業では、応募後や面接時に見学を行うケースもありますが、求職者の立場からすれば「まず見学してから応募を判断したい」と考えるのが自然です。
実際に「見学後に応募を判断していただいてかまいません」といった文言を求人票に記載している企業もあり、このような配慮は求職者が気軽に安心して見学を申し込む後押しとなります。もちろん、見学の結果として応募に至らないケースもありますが、それによって生じるロスよりも、納得のうえで応募してもらえるというメリットのほうが大きいといえます。
3.ミスマッチと早期離職の防止に役立つ
応募前の見学には、もう1つの大きなメリットがあります。それは、入社後のミスマッチを未然に防げるという点です。求人票やホームページから得た情報だけでは伝わらない現場の雰囲気や実際の業務の様子を、あらかじめ自分の目で確かめることで、「自分に合った職場かどうか」を判断することができます。
この確認がないまま応募・入社すると「思っていたのと違う」「こんなはずではなかった」といったギャップが生じやすく、早期離職につながる恐れもあります。一方、企業側にとっても、見学を通じて応募者の印象や人柄を把握できる点は大きなメリットです。見学を踏まえて応募に至った場合には、面接時の質問内容にも工夫ができ、より有意義な対話が可能となるでしょう。
受け入れ態勢と小さなサプライズで、+αの効果
会社見学当日は、一般的には会社概要や自社製品・サービスの紹介などの会社案内から始まり、その後、工場や事務所内の見学へと移る流れが多いようです。もちろん、このような基本的な内容でも一定の効果はありますが、せっかく興味を持ち、自ら足を運んでくれた求職者に対して、他社と同じような「型通り」の対応では、やや物足りなく感じさせてしまうこともあります。
だからこそ、「この会社は他とは違う」「ここで働いてみたい」と思わせるような、自社ならではの工夫、いわば「ちょっとしたサプライズ」を用意することが、企業イメージを高めるうえで非常に有効です。では実際にどのような工夫が効果的なのか、例をあげてみましょう。
1.見せたいもの、感じてほしいことを明確にする
会社見学の目的は、ただ単に現場を案内することではありません。大切なのは「どんな点を見てほしいか」「どんなことを感じてほしいか」という意図を明確にし、それが見学内容にしっかりと反映されているかどうかです。
例えば工場見学であれば、設備や作業環境、業務の流れなどハード面の説明が中心になることが多いですが、「この仕事が果たす社会的な役割」や「身に付けられるスキル」「キャリア形成の可能性」などの情報を加えることで、求職者が「自分の未来像」をより具体的にイメージできるようになります。
また、実際に働いている「人」に注目してもらいたい場合には、社員の年齢層やキャリア、担当業務、得意分野などを紹介するのも有効です。自分と重ねやすい先輩の姿を見ることで、入社後の自分のイメージをよりリアルに描くことができ、不安の軽減にもつながります。
さらに、重機オペレーターのような職種であれば、実際に運転席に座ってみる体験など、ちょっとしたアクションがあるだけでも「この仕事をやってみたい」という気持ちを大きく後押しできます。こうした体験型の工夫は、職種の魅力をダイレクトに伝える手段として非常に効果的です。自社の強みや魅力を「伝えたいメッセージ」として意識的に構成し、求職者の心に残る時間とすることが大切です。
2.入社間もない先輩社員との懇談を取り入れる
求職者が応募を迷う理由の一つに、「自分にできるだろうか」「この会社でやっていけるだろうか」といった不安があります。そうした気持ちに対して、企業側が「大丈夫ですよ」と励ますことはできますが、それだけでは十分とはいえません。
そこで効果的なのが入社歴の浅い社員や、直近で入社した先輩社員との懇談の場を設けることです。同じような背景や条件で入社し、前向きに仕事に取り組んでいる先輩の存在は、求職者にとって何よりも説得力のあるロールモデルとなります。特に未経験者の募集では、「未経験だった自分もここまでできるようになった」という体験談が、求職者にとって大きな安心材料となり、自信につながります。
また、経営者や管理職からの説明とは異なり、等身大の先輩社員の声には自然と共感が生まれやすく、企業への信頼感も高まります。こうした丁寧な対応を通じて、「この会社は働く人を大切にしている」という印象を持ってもらえることができれば、見学後の応募にもつながりやすくなるでしょう。
会社見学と求人票をベースにした面接で、納得感とミスマッチ防止を
会社見学を経て応募に至った場合、次に控えるのは選考面接です。通常、面接では「志望動機」や「自己PR」などを中心に質問が行われますが、応募前に見学を実施した応募者に対しては、まず見学内容を話題に取り上げることで緊張を和らげ、自然な雰囲気の中で面接をスタートさせることができます。
例えば、「見学して印象に残ったことはありますか?」「イメージと違っていた点はありましたか?」といった問いかけをすることで、応募者の感じたことや目的意識が見えてきます。同時に、企業側にとっても今後の見学受け入れの改善にもつながる貴重なヒントになる場合があります。
面接の序盤で場の雰囲気がほぐれたところで、本格的な質問に進みますが、その際に「求人票をベースとした質問」を取り入れることをおすすめします。求人票を読み込んだうえで応募しているかどうかを確認できるだけでなく、一般的な質問では得にくい応募者の価値観や本音を引き出すことができます。
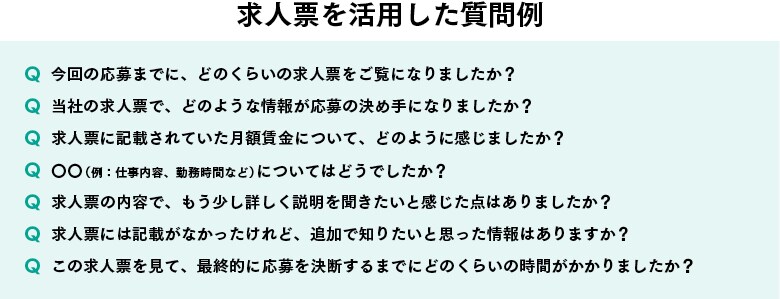
こうした質問のやりとりからは、応募者がどの程度真剣に応募を検討しているか、どのような点に魅力を感じたのか、また、仕事や職場に対してどのような価値観を持っているかが見えてきます。
例えば、賃金や福利厚生を重視する人、仕事内容に強いこだわりを持つ人、自分に合った働き方を求める人など、応募者によって重視するポイントはさまざまです。こうした価値観を面接段階で把握しておくことは、採用後のミスマッチを防ぐだけでなく、入社後のモチベーション維持や定着支援にも大いに役立ちます。
また、「志望動機は?」といった定番の質問では、応募者も構えてしまいがちですが、求人票という「共通の情報源」を軸にした質問であれば、求職者も答えやすく、より本音に近い回答を引き出せます。
さらに、応募者の回答内容からは、現在の求人票における説明が不十分な点や伝わりにくい部分、新たに追加すべき情報などが見えてきます。こうしたフィードバックは、求人票の改善につながり、自社の採用力強化にも役立つ「生きた情報」となるでしょう。
会社見学は「採用成功への第一歩」
求職者にとっての「会社見学」は、単なる職場見学にとどまらず、就職先を判断するための重要なプロセスです。その受け入れ方次第で、企業イメージの向上はもちろん、応募促進や入社後のミスマッチ防止にもつながるなど、多くのメリットが期待できます。
もちろん、受け入れには一定の手間や準備が伴いますが、わざわざ足を運んでくれる求職者は、既に自社への関心を持っている貴重な存在です。そのチャンスをどう活かすかは、企業の工夫と姿勢次第だといえるでしょう。
「Face to Face」ならではのリアルなコミュニケーションを通じて求職者の心をつかめれば、「見学」から「応募」、さらには「採用・定着」へとつながる好循環が生まれます。会社見学は、その第一歩として、企業にとって大きな可能性を秘めたチャンスなのです。
弥報Onlineでは他にも「採用」をテーマにした記事を発信しています。
採用の記事を読む

この記事の著者
弥報編集部
弥生ユーザーを応援する「いちばん身近なビジネス情報メディア」

この記事の監修者
五十川 将史(ウエルズ社会保険労務士事務所 代表)
1977年、岐阜県生まれ。明治大学卒。大手食品スーパーの店長や民間企業での人事担当者、ハローワーク勤務を経て、独立。ハローワークを活用した採用支援を専門としている。商工会議所、労働局、社会保険労務士会などでの講演実績も多数あり、これまでの受講者は1万人を超える。著書に『中小企業のためのハローワーク採用完全マニュアル』(日本実業出版社)、『ハローワーク採用の絶対法則』(誠文堂新光社)などがある。