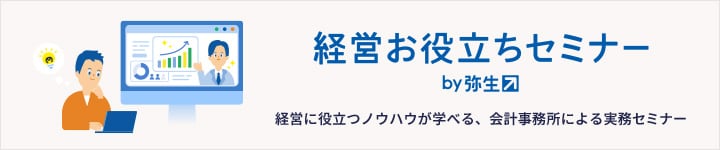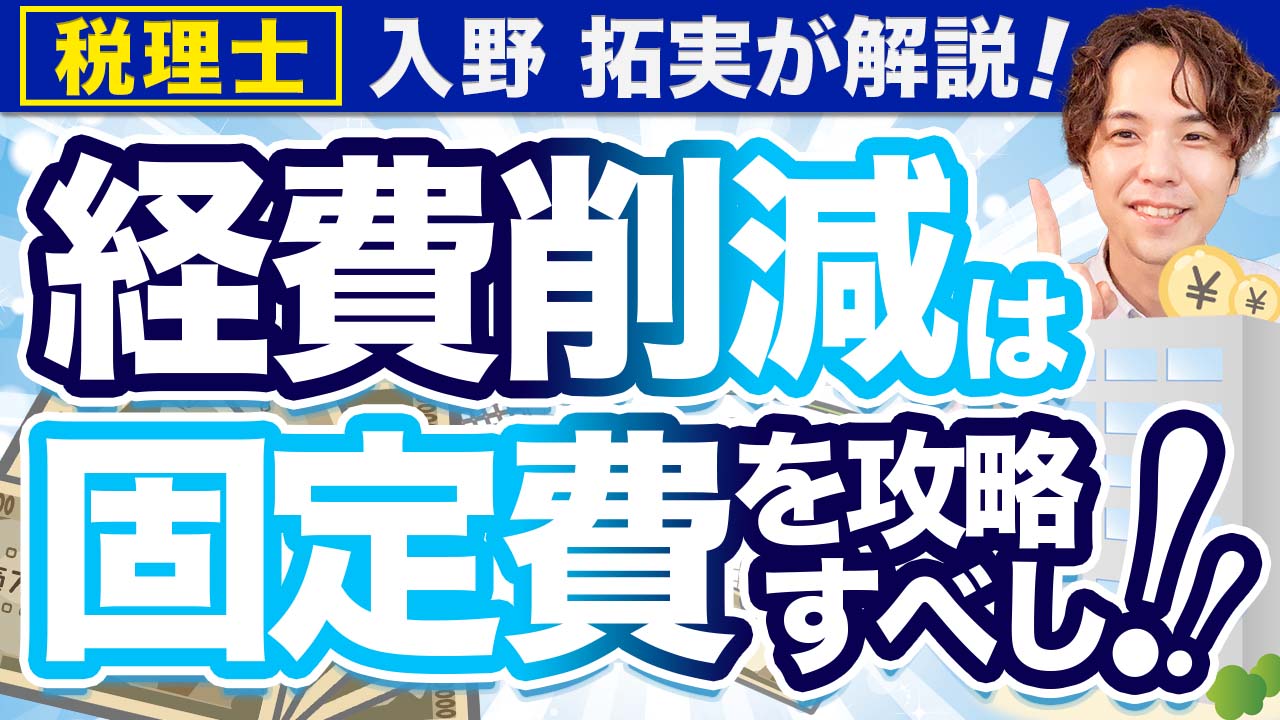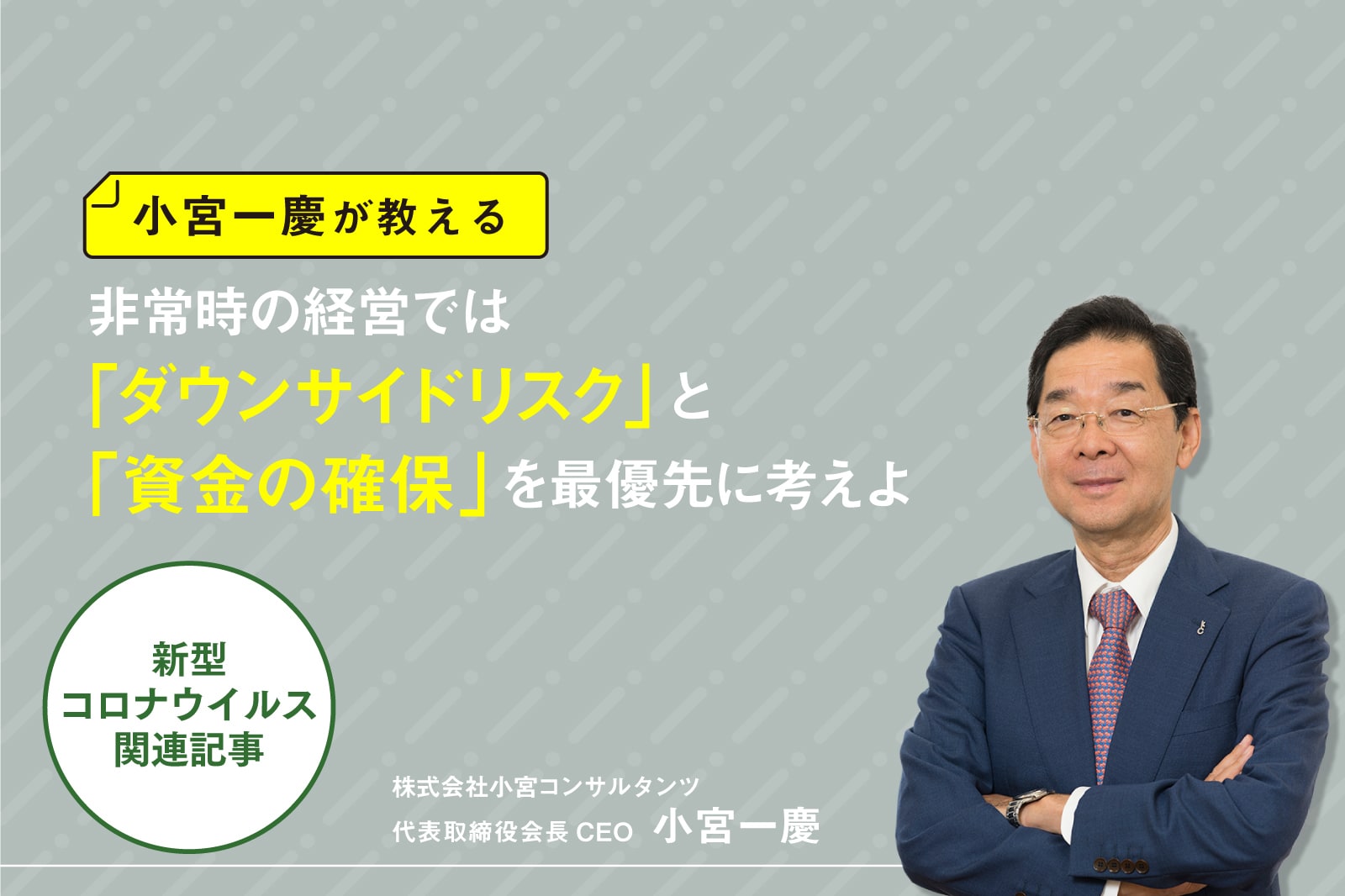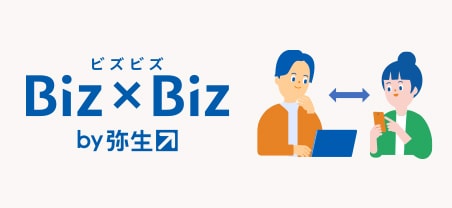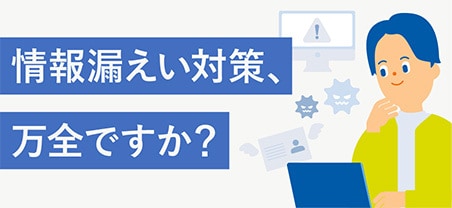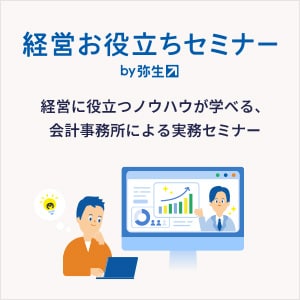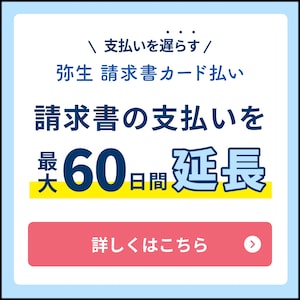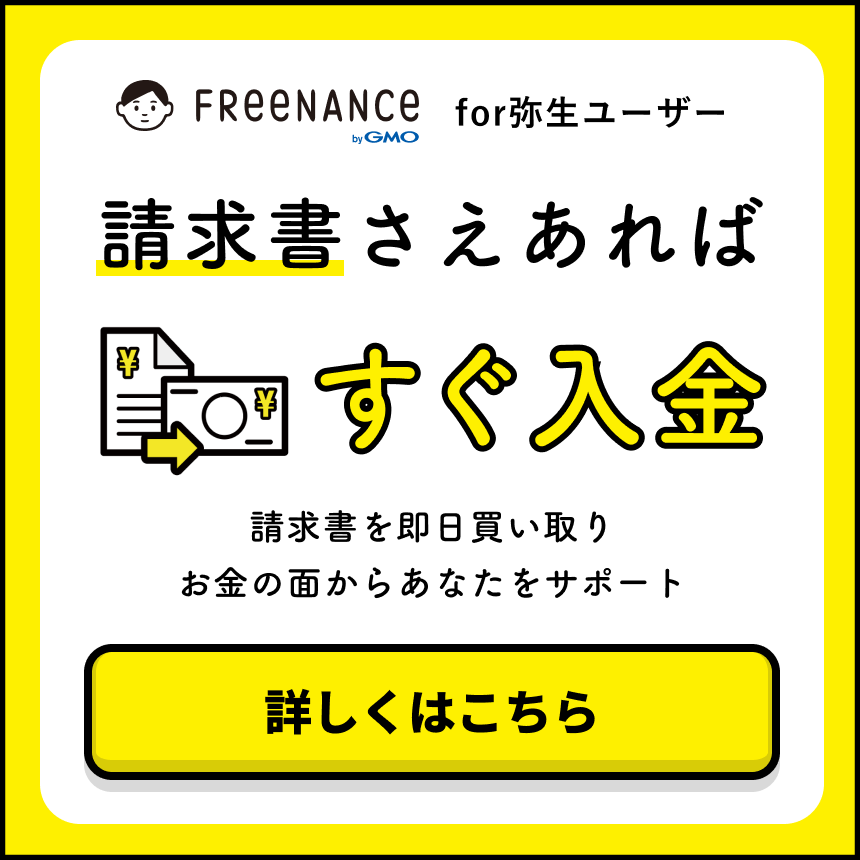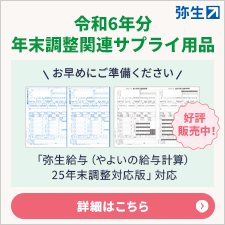- 事業成長・経営力アップ
小宮一慶が教える、経営者なら知っておくべき「発見力」を高める方法
2020.06.24

ビジネスパーソンが仕事をするうえで「物事を正確に見ること」はとても大切です。今回は、その根幹にある「発見力」とその養い方について説明していきます。また「発見力」を養うことで世界は広がり、より幸せな人生を送ることができます。中小企業の経営者の皆さんの新たな視点として、また社員教育にも役立ちますから、ぜひ覚えておきましょう。
目次
人は無意識のうちに必要・不要な情報を取捨選択している
皆さんは普段の生活において、見えているようで見えていないものがたくさんあることに気づいていますか?
例えばセブン-イレブンの店舗のロゴ「7 ELEVEn」の最後が、小文字の「n」であるのをご存じですか? あるいはローソンの看板も街なかで何度も見かけたことがあると思いますが、どんな形か思い出せますか? また看板の下のほうには「S」で始まる言葉がありますが、どんな単語かわかりますか? 正解は「STATION」です。ローソンは「駅」なのです。しかし、多くの人は意外と気づいていません。
他の例を挙げると、電車で通勤している人は駅の自動改札機を通りますが、何番の改札機を通りましたか? 出口の番号ではありません。各改札機の下部には大きな番号が振ってありますが、気づいていない人が大半ではないでしょうか。ちなみに私はゲンを担ぐので、4番や13番の改札機は極力通らないようにしています。
このように毎日何気なく何万回も見ていても、実際は見過ごしているものが多いのです。
先のセブン-イレブンの例では、セブン-イレブンに行きたい人からすれば、そのコンビニエンスストアがセブン-イレブンであると認識できればいいわけですから「n」が小文字か大文字かは関係ありません。私たちはもともとすべての情報を取ろうとはしておらず、関心のあるものだけ、自分に必要なものだけを見るようにできています。カメラで撮影するようにすべての景色をそのまま見ているわけではありません。
「必要なものを取捨選択して見ること」は、人が生きるうえで不可欠です。すべての情報を収集し分析していたら、入ってくる情報量が多くなり過ぎて何も判断できなくなります。ひょっとしたら必要な情報が見えていない可能性もあるかもしれません。
まずは情報に関心を持ち、分解してポイントを絞る

それでは「発見力」を養うために、具体的にどうすればものが見えるようになるのかを説明していきます。
まず第1ステップは「関心」を持つことです。皆さんは自動ドアを通るときに、その自動ドアのメーカーを確認しますか? 多くの自動ドアには閉じたドアの中央にメーカー名入りのシールが貼ってあります。私は必ず見ます。
なぜか? 私の顧問先企業が自動ドアを設置しているからです。水色のシールが貼ってあるとその会社の自動ドアだとわかります。同様に塾の看板があれば、どこの塾かにも注意します。百貨店では化粧品コーナーが気になります。いずれも私が社外取締役をしている会社だからです。関心があるから自然と見てしまうのです。
皆さんも好きな人のことならよく見ることでしょう。それは関心があるからです。先ほど私たちは目の前のことをすべてカメラで撮影するように見るのではなく、あらかじめ見るべきものを決めて選んで見ているとお伝えしました。つまり関心がスクリーニング(ふるい分け)をしているのです。
私は経営者の皆さんに「新聞を読むときは、国際面であろうが金融面であろうが他業種の記事であろうが、大きな記事のリード文だけは必ず読んでください」とお願いしています。それは関心の幅を広げることで、社会のことがより広範に見えるようになるからです。
次に「仮説」です。仮説とは基準を指します。基準があればものがより深く、より鮮明に見えるようになります。つまり関心を持って見えたものを、さらに何らかの基準を持って見るとよりはっきりと見えるのです。正しい仮説を持つことで「目利き」になれます。
テレビ番組『開運!なんでも鑑定団』を見ていると、鑑定者たちは数分で本物と偽物を見分けます。それは「どこをどのように見ればよいか」という見分ける仮説を持っているからです。最終的には「正しい仮説を自分で立てられるようになること」が、ものが見えるようになるということです。
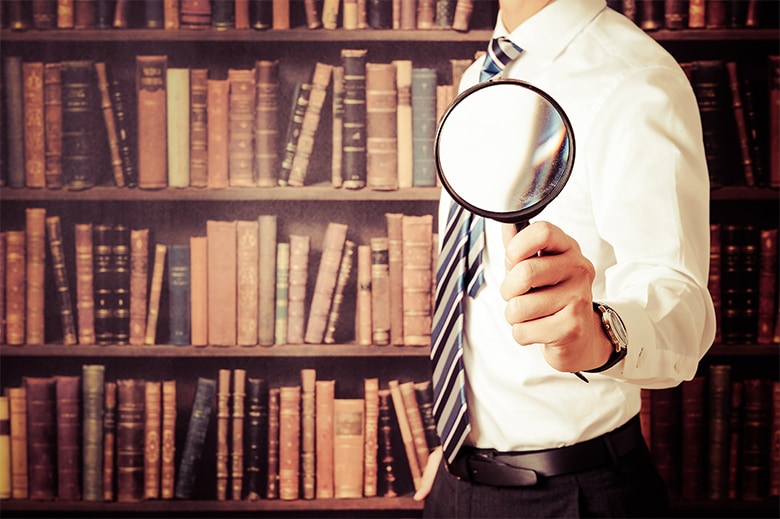
経営者の皆さんが社員を、また部署の上司が部下を指導する立場にあるのであれば、まずやるべきは、あることに関心を持たせることです。すると、ものの見え方が変わります。そのためにはヒントを与えることも有用です。次に「仮説」を立てるには、分解して見るポイントを絞ることです。これでものは見えやすくなります。
私のお客さまのアパレル企画会社の若手社員たちは、ものを深く見ています。その理由はファッションに関心があるのはもちろん、上司が若い人たちに分解して見えるコツを与えているからです。例えば「これから流行りそうな洋服を見てこい」と言われても、経験の浅い社員はどこをどう見ればいいのかわかりません。しかし「今年の流行色は黒だと言われているが、本当にそうなのか。黒い服の人の割合を見てこい」と言われれば、色に注目して見ることができます。これが関心に、仮説を与えるということです。
ものが見えないのはポイントがないからです。分解して仮説を持つことで、それまで見えなかった多くのことが見えてきます。全体を見ようとすると、ものを見ているようで見ていない状態になりがちですが、ポイントを絞れば誰でもものは見えてきます。
ここで簡単に、あるポイントを見て全体を想像する私流の仮説をいくつかご紹介しましょう。
- 朝食のサラダバーのプチトマトのヘタを取ってあれば一流ホテル
- 床がきれいな工場は良い工場
- 社員全員が「お客さま」という言葉遣いをするのが良い会社
ただし仮説を立てる際に注意すべきことがあります。仮説は立て方を間違えると、見えるはずのものが見えなくなってしまいます。私もコンサルタントになりたてのころは、お会いする経営者たちに結構騙されたものです。社長の肩書でカッコいいことを話し、腕には高そうなロレックスをしていたりすると、良い会社に間違いないと思い込んでいました。しかしロレックスは会社の業績を表すポイントではなく、私たちの誤解を誘導するレッテル(先入観)だったのです。
誰でも多かれ少なかれ、いろいろな先入観を持って人や物事を見るものです。これが間違いや誤解を生む原因となります。そこで必要なのは、まず先入観を疑うこと。そもそも自分が先入観を持っていることに気づかないところに恐ろしさがありますが、この前提は正しいのかと常に考える癖をつけると、ものの見え方は変わってきます。
さらに1度立てた仮説を常に検証し続けることも大切です。検証とはつまり、素直に観察することです。そして仮説に当てはまらないケースがあると気づいたら、潔くその仮説を捨てなければなりません。何事にも素直であることが大切です。こだわらないとものは見えませんが、とらわれるとまた見えなくなってしまう。難しいものですが素直さが重要なのです。
「発見力」を養い、正しくものが見える人は幸せになれる
ものが見えるということは気づくということでもあります。見えなければ気づくことができないものが出てきます。気づく人は誰かが困っていることに気づくので、進んで手助けできます。逆に人が喜んでいることに気づけば、一緒に喜ぶこともできます。そういう人が周りから好かれるのです。この気づく力こそが「発見力」であり、この発見力を高めると人は幸せになれるのです。

今回は仕事をするうえで重要な、物事を正確に見る、深く見るための「発見力」について説明してきました。同時にこれは経営者の皆さんに限らず、人の喜びや悲しみがわかる、見えるということが、人生を過ごすうえで大事なことなのではないかと思います。
見えたり気づいたりすれば世界が広がっていき、うれしくなりますよね。皆さんもいろいろなことを周りで発見してみてください。
【関連記事】

この記事の著者
小宮 一慶(こみや かずよし)
経営コンサルタント。株式会社小宮コンサルタンツ代表取締役会長CEO。十数社の非常勤取締役や監査役、顧問も務める。1981年京都大学法学部卒業。東京銀行に入行。1984年から2年間、米国ダートマス大学タック経営大学院に留学。MBA取得。帰国後、同行で経営戦略情報システムやM&Aに携わったのち、岡本アソシエイツ取締役に転じ、国際コンサルティングにあたる。この間、UNTAC(国連カンボジア暫定統治機構)選挙監視員として、総選挙を監視。93年には日本福祉サービス(現セントケア)企画部長として在宅介護の問題に取り組む。95年に小宮コンサルタンツを設立し、現在に至る。企業規模、業種を問わず、幅広く経営コンサルティング活動を行う一方、年百回以上の講演を行う。新聞・雑誌、テレビ等の執筆・出演も数多くこなす。経営、会計・財務、経済、金融、仕事術から人生論まで、多岐に渡るテーマの著作を発表。その著書140冊を数え、累計発行部数は360万部を超える。
資金調達ナビ
弥生のYouTubeで会計や経営、起業が学べる!
関連記事
事業支援サービス
弥生が提供する「経営の困った」を解決するサービスです。