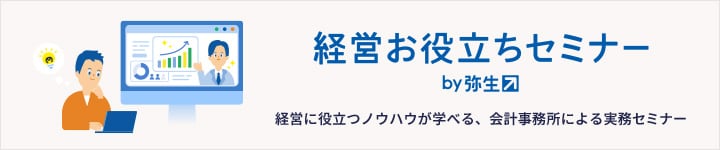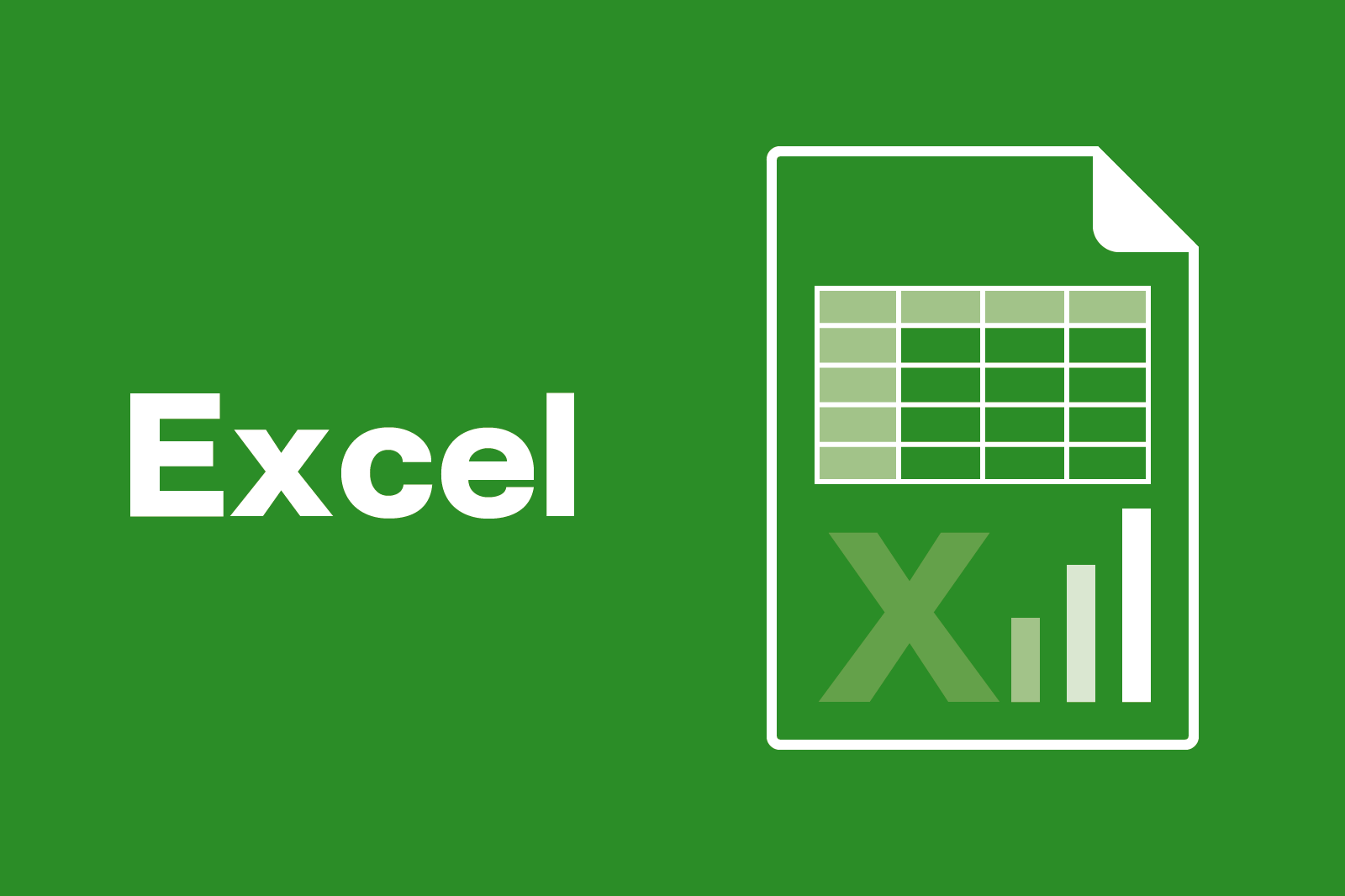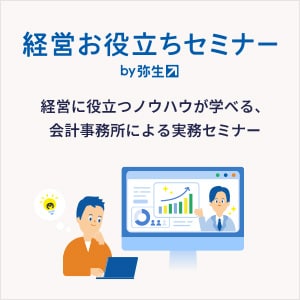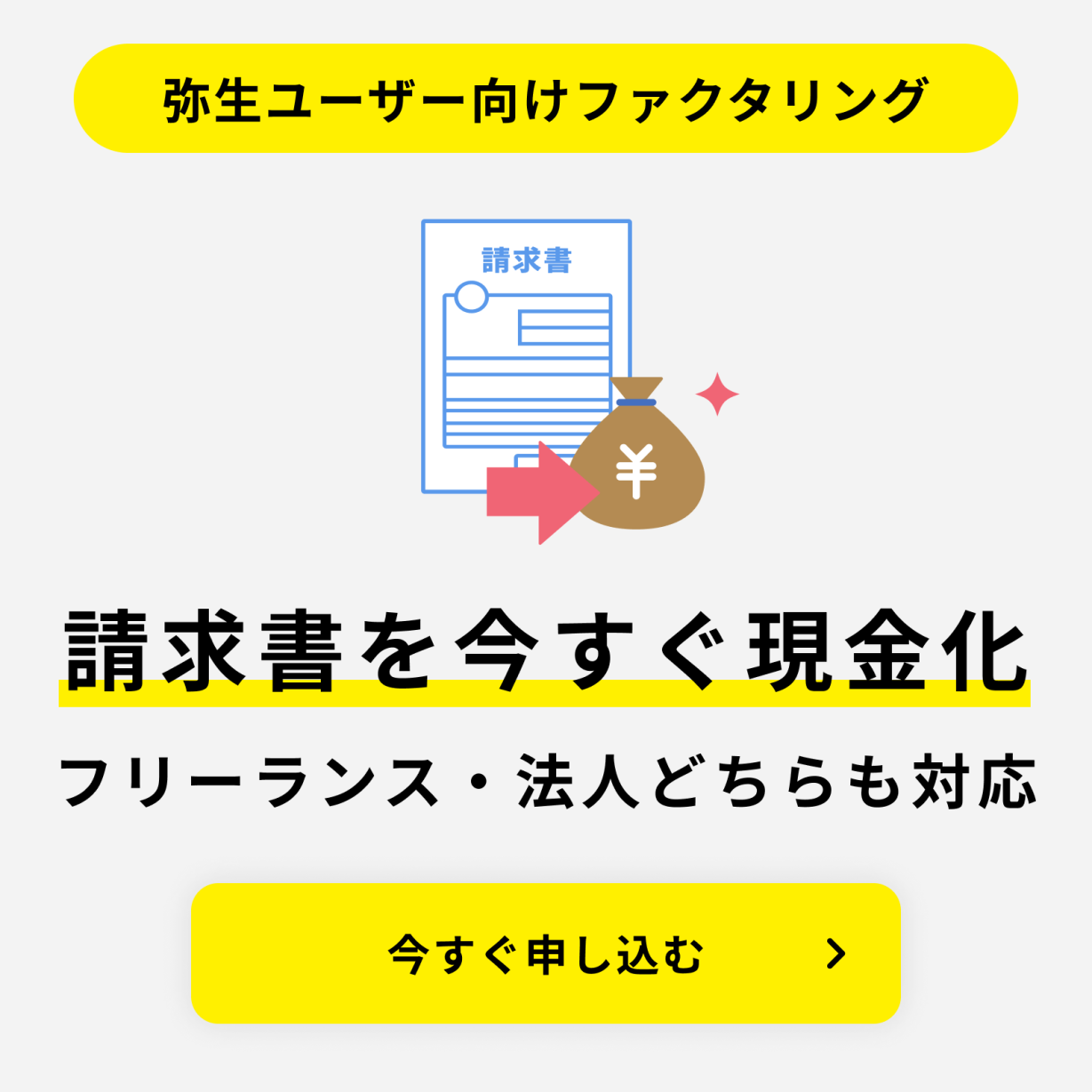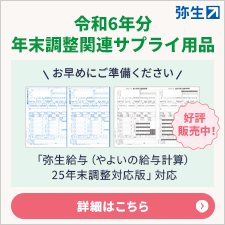- 事業成長・経営力アップ
適正な手元資金の具体的な額を知りたい!その確保の手段についても解説【教えて!吉田先生】
2025.08.12

多くの中小企業にとって、資金繰りの安定は経営の生命線です。突然のトラブルや予期せぬ経済変動に直面した際、事業を継続し成長機会をつかむためには、十分な手元資金が必要になります。
今回は、なぜ手元資金が必要なのか、そのメリットや適正な手元資金の目安、そして実際に手元資金を確保するための具体的な方法について、財務・資金調達コンサルタントの吉田学先生に伺いました。
※本記事は2025年7月時点の情報を基に作成しております。法令などの最新情報については、政府・各省庁などから出ている文書をご確認ください。
弥報Onlineでは他にも「資金調達」をテーマにした記事を発信しています。
資金調達の記事を読む
目次
なぜ手元資金が必要なのか?
中小企業にとって、財務面で最も重要な目標の一つは、資金ショートを防ぐことです。手元資金(現預金)が豊富にあれば、資金ショートのリスクを避け、安心して事業を継続できます。
突発的なトラブルや予期せぬ事態は、中小企業の事業活動に大きな影響を与え、あっという間に収益を圧迫します。例えば、コロナ禍や自然災害(地震、台風など)の際には公的支援策もありますが、それらが実際に手元に届くまでには時間がかかります。十分な手元資金があれば、そうした状況にも耐え抜くことができるでしょう。
手元資金が少ないと、経営者は常に資金繰りに追われ、本業に集中する時間まで奪われます。余計なコストや労力がかかるばかりか、ストレスも大きくなるでしょう。手元資金に余裕があれば、資金繰りの心配から解放され、その時間を本業への集中や事業の成長に充てることが可能です。
金融機関は「晴れの日に傘を貸し、雨の日に取り上げる」とよく表現されます。これは、手元流動性の高い企業、つまり手元資金が豊富な企業に対して融資をしやすい傾向にあるということです。手元資金が潤沢な企業は、金融機関からの評価も高まります。
手元資金がもたらす6つのメリット
中小企業が手元資金を増やすことには、以下のような多くのメリットがあります。
1)資金ショートの防止と経営危機回避
手元資金が潤沢であれば、突発的な事象が発生しても、経営危機を回避できます。
2)財務の安全性向上
財務体質が強化され、金融機関などからの信用力が高まります。
3)余裕をもった経営
経営者は本業に集中できます。よって、安定した意思決定も可能になります。
4)突発的なリスクへの対応力強化
急激な環境変化が起きても、手元資金があれば迅速に対応できます。
5)成長や投資機会の安定確保
新規事業参入、設備投資、人材採用など、事業成長の機会を逃さず、即座に対応が可能です。
6)資金繰りの安定化
現預金が豊富な企業は、当然ながら資金繰りが安定します。
このように、手元資金を増やすことは中小企業の経営安定、成長、そしてリスクマネジメントのすべてに直結する非常に重要な活動といえるでしょう。
適正な手元資金はどれくらい必要ですか?
適正な手元資金の額は、企業の状況によって異なりますが、まずは一般的な目安について解説します。ここには著者の持論も含まれますが、1つの目安としてください。
原則として、月商の1か月分を手元資金の最低目標としましょう。しかし、1か月分では突発的な問題が発生した場合に資金ショートするリスクが高いため、できれば月商の2~3か月分の保有を目指してください。例えば、月商が1,000万円の企業であれば、2,000万円から3,000万円の現預金が目安としましょう。
また、月商だけでなく、「固定費ベースで3か月以上」(借入金返済額なども含む)などと設定することも有効です。業種によっては「固定費の半年分」などと目標設定するのも良いでしょう。さらに、以下のような場合は、より多くの手元資金が必要となる場合があります。
| ・売上の入金サイトが長い(売掛金の回収に時間がかかる)業種 ・在庫を多く抱える業種・成長ステージにあり、仕入れや人件費が先行して増加する企業 ・大震災やコロナ禍のような予測不能な災害、または大手取引先の倒産など、 不測の事態に備える場合 など |
具体的な目標設定をする場合は、顧問税理士などの専門家に相談することをお勧めいたします。
どのように手元資金を確保すればよいですか?

手元資金を増やすためには、主に以下の4つの方法が考えられます。
1. 売上・利益の確保
最も基本的な方法は、本業でしっかりと利益を上げることです。
〈具体的な方法〉
- 売上増加やコスト削減によって、営業活動から得られるキャッシュを増やしましょう。
- 過度な節税に偏らず、法人税を納めたうえで適切に利益を残すことが重要です。
- コスト管理を徹底し、原価低減や間接費の削減にも取り組みましょう。
- 過剰在庫の適正化を図ることも、資金繰り改善につながります。
- 遊休資産や事業への貢献度が低い不動産の売却も、手元資金確保の一案です。
2. 売上債権の早期回収
売掛金の回収期間を短縮することで、手元資金を増やすことができます。
〈具体的な方法〉
- 取引先との取引条件を見直す交渉を粘り強く行いましょう。
- 新規取引先を開拓する際は、回収期間を短く設定するような交渉を検討してください。
- ファクタリングの活用も一案です。積極的にお勧めするものではありませんが、資金繰りが苦しいときに依存するのではなく、日ごろから早期現金化を目指す手段として活用することは有効です。
(参考)
請求書を早期資金化|弥生株式会社
3. 買掛金へのアプローチ
キャッシュアウトのタイミングを後ろ倒しにすることで、手元に資金を残す方法もあります。例えば、請求書カード払いというサービスは取引先から受け取った請求書をクレジットカードで支払えるサービスです。
カード決済で支払うことで、銀行振込で支払うよりも実質的なキャッシュアウトを最大60日後まで繰り越すことができます。
4. 資金調達
外部からの資金調達も手元資金を増やす有効な手段です。
〈具体的な方法〉
1)融資
日本政策金融公庫、保証付き融資、民間金融機関からの融資などを検討しましょう。
2)新しい資金調達手段
オンラインレンディング(AI融資など)、クラウドファンディングなども選択肢になります。
3)補助金・助成金
返済不要ですから、積極的に活用を検討すべきです。手元資金増加に貢献します。
4)VC投資/エンジェル投資
ベンチャー・成長志向系の企業にとっては、資本増強も手元資金増加に貢献します。
5)保険や公的共済
いざというときに「契約者貸付」を利用でき、即座に手元資金を増やすことが可能です。
6)経営革新計画などの法律承認
信用保証枠の別枠が設定されるなど、資金調達余力を強化できる場合があります。
(参考)
経営革新支援|中小企業庁
さまざまな意見があると思われますが、月商の3か月分に達するまで「金融機関から借りられるときに借りておく」という考え方も、あながち間違いではありません。
自社だけでは対応が難しいです。どうすれば?
ここまで手元資金の重要性と確保策について解説してきましたが、「頭では理解できるけれど、実際に自社で実践するのは難しい……」と感じる経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような時は決して1人で抱え込まず、専門家の力を借りることをお勧めします。また、まずは顧問税理士にご相談してください。もし難しい場合は、融資や資金調達、キャッシュフロー改善を専門とするコンサルタントに相談してみてください。
弥報Onlineでは他にも「資金調達」をテーマにした記事を発信しています。
資金調達の記事を読む

この記事の著者
弥報編集部
弥生ユーザーを応援する「いちばん身近なビジネス情報メディア」

この記事の著者
吉田 学(よしだ まなぶ)
財務・資金調達コンサルタント
株式会社MBSコンサルティング 代表取締役。1998年の起業以来、「資金繰り・資金調達支援」に特化して創業者や中小事業者を支援。これまでに1,000 社以上の資金調達相談・支援を行い、その資金調達支援総額は20億円超。主な著書に、「社長のための資金調達100の方法」(ダイヤモンド社)、「究極の資金調達マニュアル」(こう書房)、「税理士・認定支援機関のための資金調達支援ガイド」(中央経済社)、「税理士だからできる会社設立サポートブック」(第一法規)などがある。
また、全国の経営者・士業などを対象にした会員制の資金調達勉強会「資金調達サポート会(FSS)」を主催している。