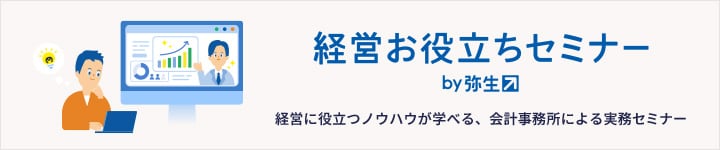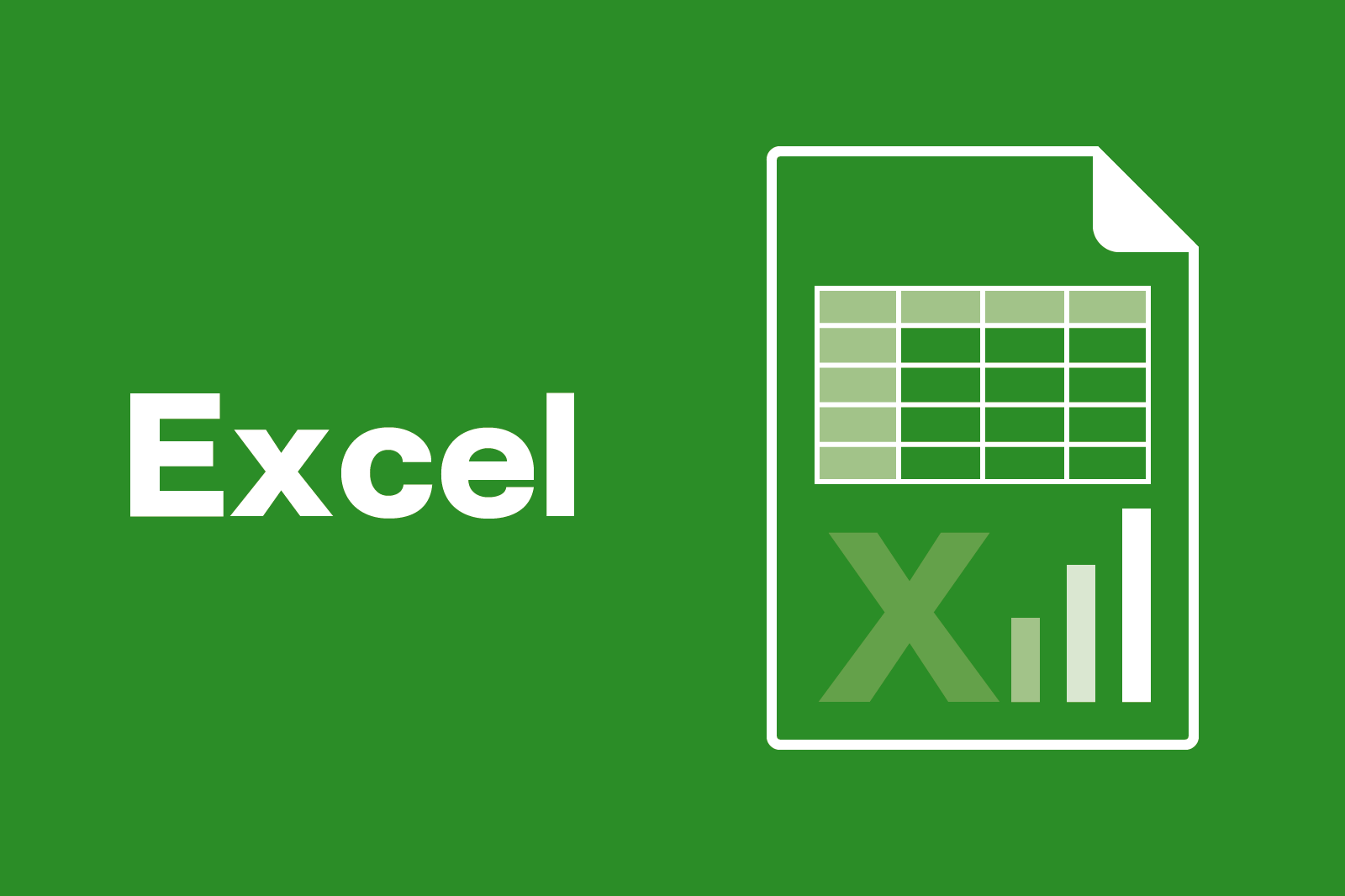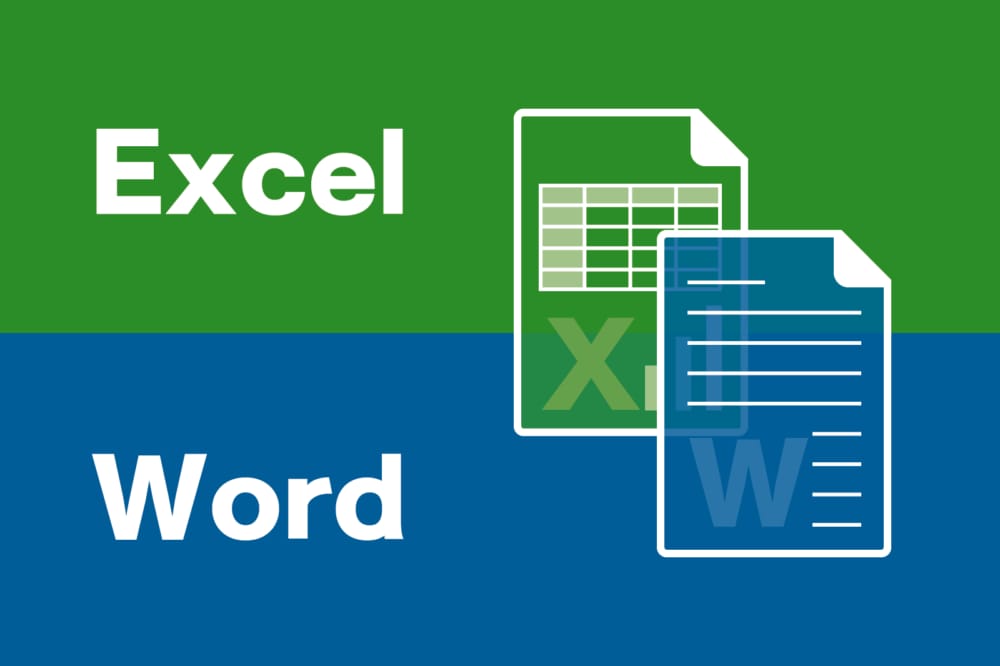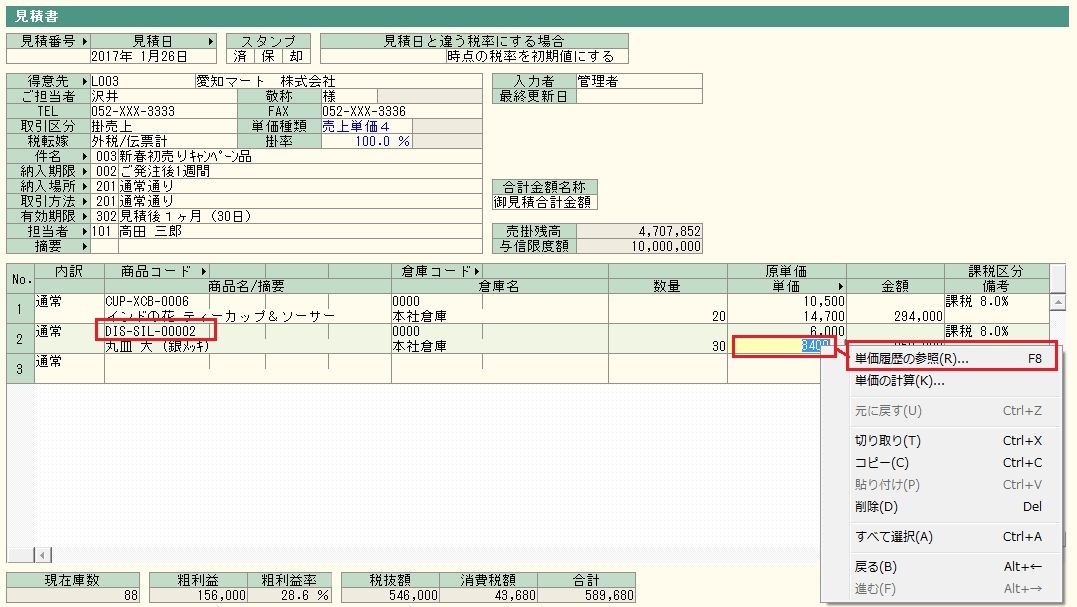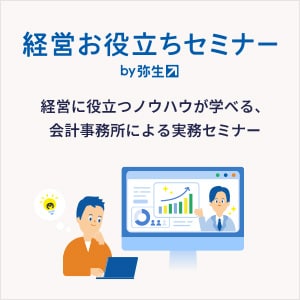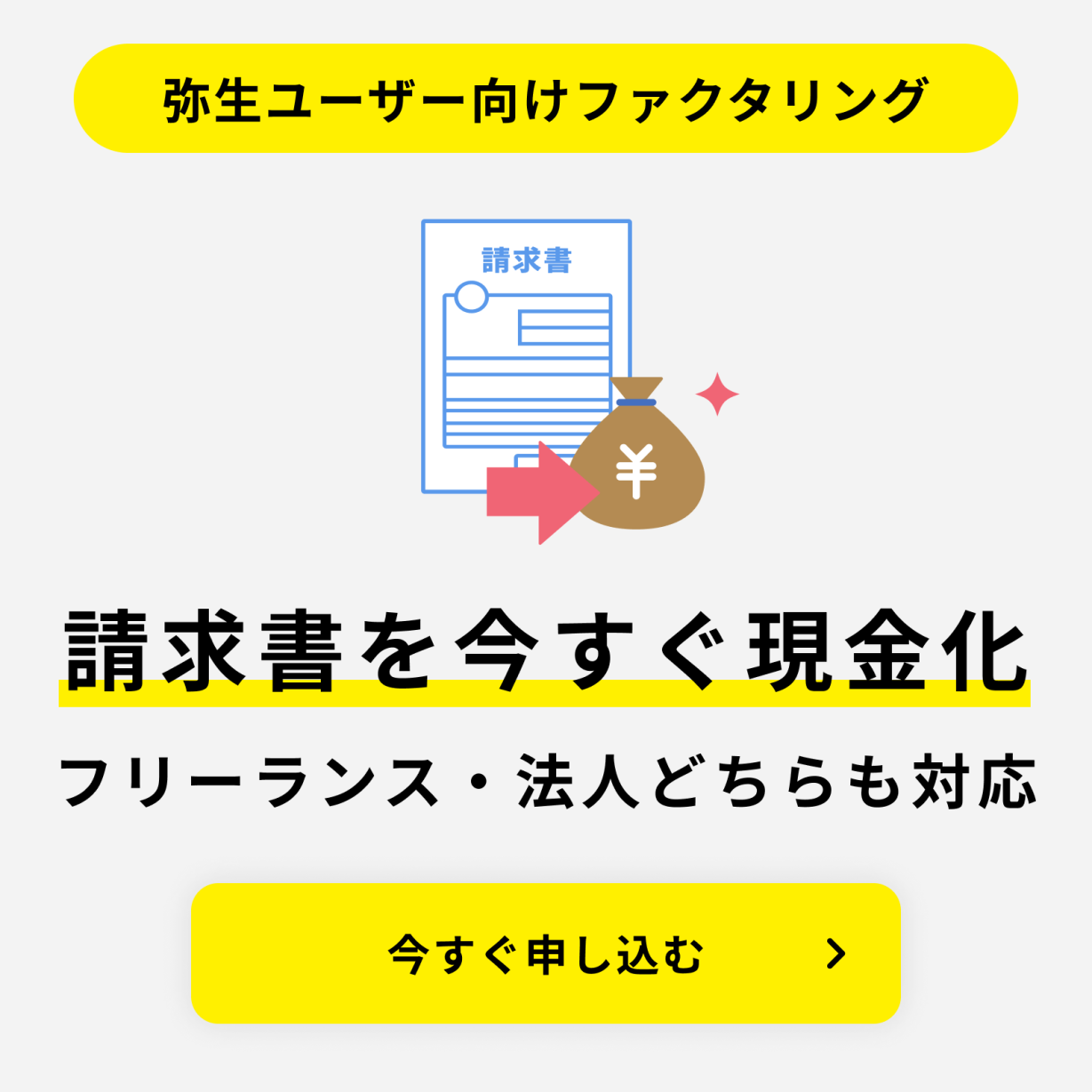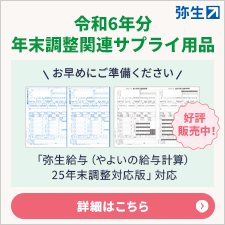- 人材(採用・育成・定着)
リモート面接の成功法則!オンラインで効果的な面接構成と評価方法
2025.05.08

コロナ禍の影響もあり、急速に普及したリモート面接は、今や採用活動に欠かせない手法の一つです。場所を選ばず実施できる利便性から、多忙な経営者や複数の企業の選考を受ける応募者双方にとって、大きなメリットがあります。
しかし、リモート面接では、面接の準備や評価方法を対面の面接以上に工夫しなければ、応募者を適切に評価することが難しくなる場合があります。今回は、株式会社ジェイックの佐藤裕康さんに、効果的なリモート面接の構成と評価方法、注意点などについて解説いただきました。ぜひ参考にしてみてください。
弥報Onlineでは他にも「採用」をテーマにした記事を発信しています。
採用の記事を読む
目次
情報量が限られる!リモート面接を成功させるための注意点
「リモート面接」は、スケジュール調整が容易で、遠方の応募者にもリーチできるなど多くのメリットがあります。
一方で、コミュニケーション自体はパソコンの狭い画面を介して行われるため、企業・応募者双方が得られる情報は、対面面接に比べると限られてしまいます。
例えば、対面面接の場合、応募者は面接の前後でオフィスの雰囲気を感じたり、面接担当者とのたわいない雑談を通じて社風や社員の魅力を知ったりすることができます。同様に面接担当者も、応募者との面接前後のやりとりを通じて、履歴書や職務経歴書だけではわからない、定性的な情報を得て評価に活かすことができます。
リモート面接では、このような応募者が感じる企業や社員の魅力、企業側が得る応募者の評価情報が限られるため、魅力付けや応募者の評価を十分に行えないことがあります。これらのデメリットを克服するためには、以下の2つのポイントを意識することが重要です。
面接担当者の「画面越しの印象」を高める
リモート面接では、面接担当者の「画面越しの印象」が応募者の志望度を大きく左右する重要な要素となります。スムーズな面接を実施するためには、オンライン環境の整備が不可欠です。
加えて、担当者の表情や反応が伝わるカメラの配置も重要です。複数の担当者で対応する際には、面接担当者1人ひとりの顔がわかるような実施体制が整えられることも求められます。画面越しのコミュニケーションの中で、面接担当者の印象を最大限に高める工夫をするとよいでしょう。
応募者の本音や人柄を引き出し「言葉以外」の情報も評価に活かす
先に述べた通り、リモート面接では、対面面接に比べて応募者から得られる感情や熱意などの定性的な情報が減少します。そのため面接担当者は「論理立てて話ができているか」「発言内容が評価できるか」といった、応募者の「話の内容」に偏った評価をしがちです。
例えば、転職理由を深掘りする質問など、応募者の感情や内面の動きを探りたい場合には、画面越しでは細かな感情の機微を読み取ることが難しくなり、評価の精度が低下することがあります。リモート面接ではこの傾向を理解したうえで、画面越しでも応募者の本音や人柄を引き出せる面接構成や、かかわり方を工夫して、言葉の内容以外から得られる情報を増やすことが重要です。
リモート面接の環境作りは、反応や表情を伝えられるかがカギ!
リモート面接で応募者に良い印象を持ってもらうには、面接担当者の反応や表情がしっかり伝わる環境を整えることが重要です。ポジティブな反応を示すことで応募者は安心し、自己表現がしやすくなります。
その結果、「自分の話を丁寧に聴いてくれた」と感じ、面接担当者に好印象を持つとともに、企業への志望度も高まります。リモート面接の環境作りにおいて、特に意識すべきポイントを紹介します。
面接担当者1人ひとりの顔を見せられる体制を整える
複数の面接担当者で対応する場合は、1人1台のカメラ付きパソコンを使用し、応募者が各担当者の顔をしっかりと認識できる環境を整えましょう。
1台のカメラで複数人を映すと、応募者にとって表情が見えにくくなるだけでなく、だれが話しているのかわかりづらくなり、面接に集中しにくい状況を生んでしまいます。
複数の面接担当者が同時に話し始めると、応募者が聞き取れずに困惑する可能性もあるため、事前に質問の時間配分を決めたり、進行役となるファシリテーターを設定したりすることが重要です。応募者が面接担当者1人ひとりの顔を認識しながら、1対1で会話している感覚を持てる環境を整えましょう。
カメラは目線の高さに揃え、カメラ目線で話す
リモート面接では、カメラの位置が低いと応募者に威圧的な印象を与えてしまうことがあります。応募者が萎縮せず自信を持って話せる環境を整えるために、面接担当者のカメラを目線の高さに配置しましょう。外部カメラの使用やパソコン台で高さを調整するのも有効です。
面接中は画面に映る応募者の顔を見てしまいがちですが、応募者の顔を見ると、応募者側から見たときに目が合わなくなってしまい、不安感を与えてしまいます。応募者に「目が合っている」と感じてもらうためには、応募者の顔ではなくカメラを見て話すようにしましょう。
応募者の画面を縮小してパソコンのカメラの下に持ってくると、応募者とカメラを同時に見ることができます。ダブルモニターを使用して履歴書やメモを確認する際は、目線が大きくずれるため、事前に応募者へ伝えておくとスムーズな進行につながります。
応募者側から見て、面接担当者の顔や表情がしっかり伝わる環境が整っているかどうかを、事前にテストしておくことも有効です。社員に応募者役を務めてもらい、カメラの位置や目線の配り方が好印象につながるかを確認し、率直なフィードバックを得ておきましょう。
応募者の本音や人柄を引き出す、効果的な面接構成

対面面接に比べ、応募者の本音や人柄が見えにくくなるリモート面接では、面接担当者がいかに、応募者の本音や人柄を引き出せるかが重要です。ここでは、そのための効果的な面接構成をご紹介します。
面接は1時間に設定、アイスブレイクや雑談を意識的に取り入れる
リモート面接は応募者の移動時間が不要で、柔軟に気軽に面接を組みやすく、30分程度の面接も可能です。しかし、応募者の本音や人柄を引き出すためには、面接時間を1時間程度と少し余裕を持って設定するのが理想的です。
そして、冒頭の企業説明の前にアイスブレイクや、ヒアリングの途中に雑談を取り入れると面接の雰囲気を和らげるので、応募者が自己開示しやすくなり、履歴書や職務経歴書からは読み取れない応募者の人柄を感じられる情報を得ることができます。活用しやすいアイスブレイクや雑談の話題は以下の通りです。
1.世間話(天気や最近のニュースなど)
当日や最近の天気、ちょっとした身近なニュースなどは、アイスブレイクの鉄板の話題となります。特に遠方の応募者の場合、天気や気温の差は実感しやすく、親しみやすい話題です。
「今日こちらは雨で大変なのですが、そちらの天気はいかがですか?」「ここ数日で一気に夏らしくなりましたね。そちらも暑いですか?」と声をかけるとよいでしょう。
2.応募者の趣味・特技など
趣味や特技に関する話題は会話が弾みやすいうえに、共通点がある場合は親近感を持ってもらえるため自己開示や安心感につながります。また、「履歴書をしっかり見てくれている」と応募者に伝わるため、企業や面接担当者に対する信頼度も上がります。
3.面接担当者の自己紹介
応募者の自己紹介の前に、採用担当者から自己紹介をすることで、応募者も自分のことが話しやすくなります。その際は、「相手との共通点を盛り込んだ自己紹介」をすることによって、親近感を持ってもらえます。
「本日〇〇さんの面接を担当する〇〇部の◯◯と申します。私も◯年前に中途で入社しまして……(省略)。今日はどうぞよろしくお願いします。」や、「履歴書で拝見しましたが、私も前職では○○さんと同じ△△業界に勤めていたので、中途入社した当初はビジネススタイルの違いに戸惑ったものです。」
など、自己紹介の内容に応募者との共通点を取り入れると良いでしょう。
ヒアリングの合間に、「フィードバック質問」を取り入れる
応募者の本音や人柄を引き出すために、「フィードバック質問」を活用することも効果的です。これは、応募者の回答やコメントに対して「●●さんの強みは、私からはこう見えましたが、ご自身ではどう感じますか?」「お話を伺った前職でのご経験は、●●さんにとって忍耐力が試された部分もあるのかなと感じましたが、いかがでしょう?」「今のご回答、他の回答に比べ、少し自信がないようにも見えましたが、何か気掛かりな点がございましたか?」といった形で、応募者の「見え方」に関するフィードバックを返しながら、相手の反応を引き出す質問方法です。
このアプローチを取り入れることで、一問一答形式のやりとりでは表れにくい応募者の微妙な感情の揺れや心理が見えてきます。また、フィードバックに対する応募者のリアクションから、自己認識の仕方や価値観、性格特性などを推察することも可能です。さらに、こうした質問を通じて応募者が自身の考えを整理しながら話すことで、より本音に近い言葉を引き出せる点もメリットです。
リモート面接で応募者の評価情報を増やす質問術
一次面接からリモート面接を積極的に導入している企業では、質問に対する応募者の受け答え方や話し方を通じて、自社に合う人柄かを判断しています。
例えば、規律性や準備力を判断するために、面接の中で「自己紹介」「自己PR」「前職を退職した理由」など、事前に準備しやすい基本的な質問を行います。応募者の視線が泳ぐことなく、スムーズに受け答えできるかどうかで、準備の度合いを判断することが可能です。この方法は、技術職や事務職、プロジェクト管理、ルート営業など、計画性や正確性が求められる職種のリモート面接で特に有効です。
逆に、臨機応変な対応力やコミュニケーション能力を重視する企業では、準備しやすい基本的な質問ではなく、「今まで頑張ってきたことは何ですか?」「前職ではどのような経験をしてきましたか?」といったオープンクエスチョンを冒頭から投げかけています。
さらに、応募者の本音や価値観を引き出すために、学生時代の経験を雑談のように深掘りする企業もあります。「高校時代にその部活を選んだ理由は?」「大学時代の研究テーマは?」といった質問を通じて、応募者の意思決定のプロセスや考え方を見極めることができます。
リモート面接と対面面接を使い分けて、自社の求める人材を採用しよう!
ここまでリモート面接の効果的な実施方法を紹介してきましたが、リモート面接と対面面接の特性を理解し、目的に応じて適切に使い分けることが重要です。応募者のモチベーションが低下する前に早期に面接を実施したり、遠方の応募者に負担をかけずに選考を進めたりする場合、対面での二次面接につなげる目的で見極め・魅力付けを行う場合には、リモート面接が有効です。
また、入社後もフルリモートで働く場合や、オンライン商談や会議が多い職場は、オンラインでの立ち居振る舞いやツールの使いこなしを評価することもできるでしょう。一方、オフィス勤務が基本の職種や、合否を決定する最終面接の場合、面接担当者の対面での熱意や社内のリアルな雰囲気を通じて応募者の志望度を高める必要がある場合は、やはり対面面接が適しています。リモート面接のメリット・デメリットを踏まえ、意図的に使い分けて活用しましょう。
弥報Onlineでは他にも「採用」をテーマにした記事を発信しています。
採用の記事を読む

この記事の著者
弥報編集部
弥生ユーザーを応援する「いちばん身近なビジネス情報メディア」

この記事の監修者
佐藤 裕康(FutureFinder®メディア事業部長)
ジェイック入社後、中途採用支援からキャリアをスタート。その後は、マーケティング部門の立ち上げ、組織マネジメントを経て、2016年にダイレクトリクルーティングと求人メディアの2つの特徴を併せ持つ新卒採用メディア「Future Finder®」の立ち上げを担当。2020年に同事業部の事業部長に就任。