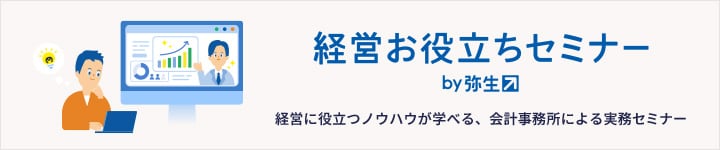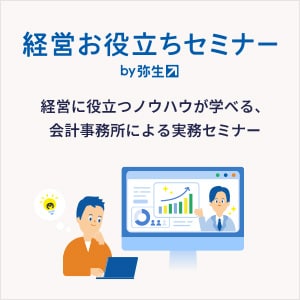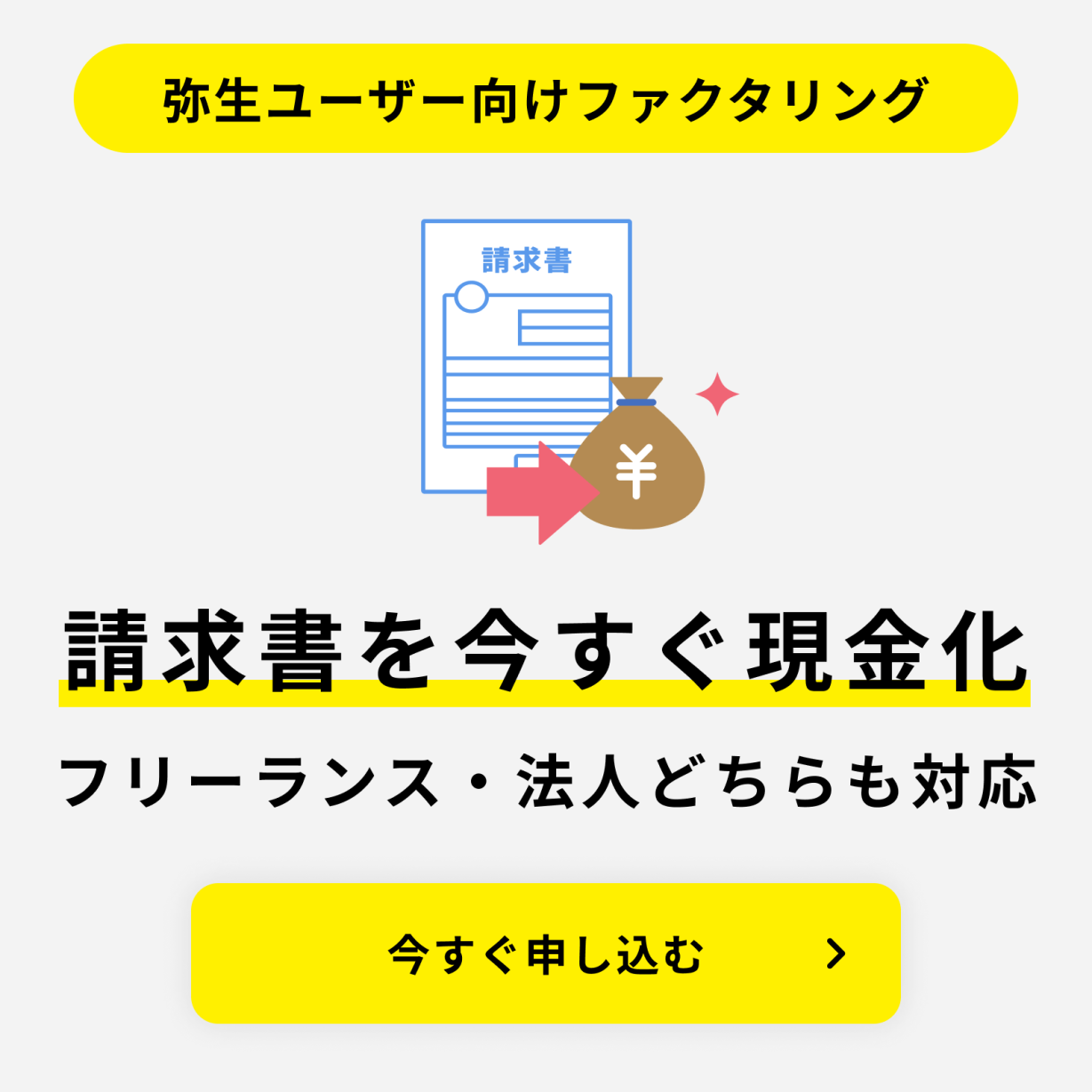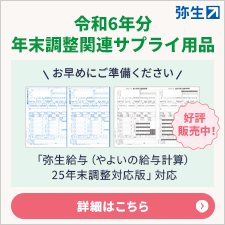- 人材(採用・育成・定着)
意外と知らない?ハローワーク求人システムの便利機能3選
2025.02.20
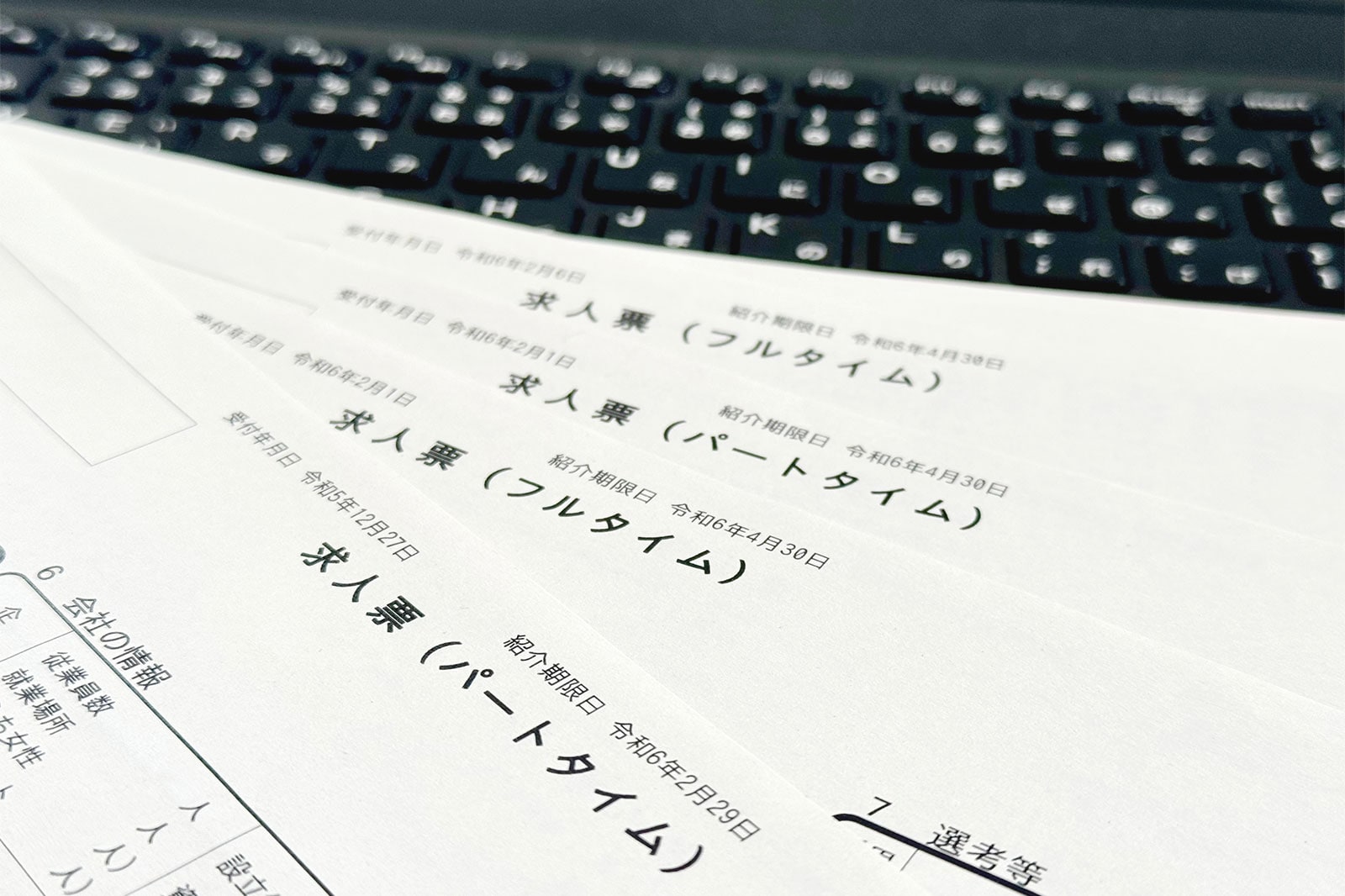
ハローワークの求人システム(以下、求人システム)は、2020年1月に大幅な刷新が行われました。この改定により求人票の様式が変更され、記載できる情報量が大幅に増加したほか、企業の求人申し込みがオンラインで可能になるなど、利便性が格段に向上しています。また、求職者が利用する「ハローワークインターネットサービス」もリニューアルされ、双方にとって使いやすい仕組みが整備されました。
しかし、求人システムに搭載されている多くの機能の中には、企業にあまり知られておらず、十分に活用されていないものが存在します。今回はウエルズ社会保険労務士事務所 代表の五十川将史さんに、求人システムの仕組みと主要な機能の説明に加え、中小・小規模企業が「いい人材」と出会い、採用につなげるための効果的な活用法を紹介いただきました。
弥報Onlineでは他にも「採用」をテーマにした記事を発信しています。
採用の記事を読む
目次
ハローワーク求人システムの仕組みと主要機能

ハローワークの求人システムは、企業が求職者と効率的にマッチングするための公的なプラットフォームです。このシステムは、求人情報のオンライン管理や詳細な情報発信を可能にする機能を備え、企業の採用活動を全面的にサポートします。また、無料で利用できる点も大きな魅力であり、多くの企業が利用しています。求人システムを活用するにあたり、下記の仕組みやポイントを踏まえるとより結果につながりやすいでしょう。
「求人者マイページ」機能
企業がハローワークの求人システムを最大限に活用するためには「求人者マイページ」を開設することが不可欠です。このマイページを利用すれば、求人票の作成や仮登録がオンラインで完結し、ハローワークのチェックを経て公開されます。公開後の求人内容の修正や公開の一時保留や取り下げも簡単に行えるほか、事業内容や会社の特長、従業員数の編集も可能です。
従来、ハローワークへの訪問や電話で対応していた手続きがオンラインで完結するため、採用活動の効率化が大幅に進みます。また、以下のような便利な機能も備わっています。
- ハローワークから紹介された応募者の一覧確認
- 選考結果の報告
- セミナーや就職面接会の情報受信
- 助成金制度や法改正の連絡受信
これらはすべて求人者マイページ上で管理できるため、採用活動がよりスムーズになります。
詳細な求人情報の掲載機能
ハローワークの求人システムは2020年の改訂により、企業が求職者に向けてより充実した情報発信を行えるよう、大幅な機能拡充が行われました。詳細は以下の通りです。
1.情報量が増えた求人票
求人票に記載可能な情報量がこれまでのA4片面から両面に拡大され、「仕事内容」欄は297文字から360文字、「求人に関する特記事項」欄は424文字から600文字へ増加しました。さらに「在宅勤務」「復職制度」「受動喫煙対策」「固定残業代」など、近年注目される項目が新たに追加されました。これにより、事業所が自由に記載できる情報量は約2,000文字にもおよび、多様な求職者ニーズに応えるための詳細な情報発信が可能となっています。
2.求人・事業所PR情報
求人者マイページでは、求人票とは別に「求人・事業所PRシート」を作成できます。このPRシートでは、研修制度や福利厚生、仕事と家庭の両立支援といった取り組み、障害者支援に関連する設備情報(例:エレベーターの有無など)を詳しく紹介することができます。
特に「事業所からのメッセージ」欄(600文字)は、求人票で伝えきれない企業の魅力や社長の想いを、求職者に届ける貴重な場として非常に有効です。ただし、このPR情報は求人票とは別表示となり、「詳細を表示」ボタンをクリックして確認する必要があります。そのため、重要な内容はできる限り求人票本体に記載することがポイントです。
実は知られていない?3つの便利機能と活用ポイント

ハローワークの求人システムには、基本的な機能以外にも多くの便利な機能が搭載されています。厳しい採用環境では、ただ求人票を公開して応募を待つだけではなく、これらの機能を活用することで、人材確保の可能性を広げられます。
今回は、特に知名度が低い3つの機能を紹介し、それぞれの内容とメリット、注意点について解説します。
自社のWebサイトを補完する画像情報機能
この機能は、求人票にリンクする形で最大10枚の画像と簡単なコメントを登録できるもので、求人票の付加価値を高める役割を果たします。求職者が求人票に興味を持った際、多くは企業のWebサイトを訪れて応募を検討するため、企業の採用活動においてWebサイトは重要な情報源です。しかし、中小・小規模企業では独自のWebサイトを持たない場合、あるいは開設していても内容が不十分であることが多く、求職者の応募意欲を削いでしまうこともあります。
またWebサイトがあったとしても、求人票との連携が弱いケースも少なくありません。企業案内や事業内容が中心となり、求職者が知りたい情報が不足している場合、採用のアピール効果が十分に発揮されない可能性があります。この画像情報機能はWebサイトの有無にかかわらず、文字情報だけの求人票を補完し、視覚的なアピールを加えることで求職者の関心を引きつける効果があります。
■活用ポイント1.求職者目線による画像選び
登録する画像は、求職者の目線に立ち、職場の雰囲気や社員の働く姿を伝える内容が求められます。実際には、本社や工場の外観、製品・商品、設備などが掲載されることが多いですが、これでは一般的な企業案内の延長に過ぎません。特に、若い人材を募集する場合は若手社員の活躍する姿、即戦力を求める場合は専門的な作業風景を中心に、「人」を主役とした写真を選ぶことが重要です。また、以下のような画像が効果的です。
- 働いている社員の様子がわかる画像
- 職場の環境が伝わる画像
- ランチや懇親会、社内イベントの風景
このような画像は、Webサイトでは対応できない求職者特化の情報として差別化を図ることができます。
■活用ポイント2.募集内容に応じた画像の更新
画像情報は一度登録したら終わりではなく、募集内容や時期に合わせてリニューアルが必要です。例えば、女性やシニアの応募を期待している求人でスーツを着たサラリーマンの画像ばかり掲載すると、求職者が応募をためらう可能性があります。求人者マイページでは、画像を自由に差し替えられるため、募集職種や求める人材に応じた更新が効果を高めます。また、古い画像を使い続けることで、企業の印象が悪くなる場合もあるため注意が必要です。
■機能上の注意点
現在の求人システムでは、登録した画像は拡大されないため、被写体が小さすぎる写真や文字入りの画像、パンフレットは避けることをおすすめします。代わりに、人物やシーンが大きく映ったものを選びましょう。また、画像1枚ごとに30文字以内のタイトルとコメントを設定できます。単なる説明ではなく、応募者に向けたメッセージ性のあるコメントを添えることで、さらに効果的なアピールが可能になります。
直接リクエスト機能
直接リクエスト機能は、企業がハローワークを介さずに求職者に直接応募を促すメッセージを送信できる仕組みです。これは、民間求人サイトのスカウトメールに相当するもので、求職者に対して企業から積極的にアプローチできるため、待ちの姿勢にとどまらない採用活動が可能となります。
従来はハローワークの窓口で希望する求職者を選び、求人票を郵送する手続きを行う必要がありましたが、直接リクエスト機能を利用すれば、この手間を省略できます。まず、求人者マイページを通じて公開を希望する求職者を検索し、応募を促したい相手にメッセージを送信します。このメッセージには企業の紹介やリクエストの理由を記載することもでき、企業の魅力や熱意を求職者に直接伝えることが可能です。
■活用ポイント
直接リクエスト機能には、以下の条件があります。
- リクエスト可能な人数:1求人につき最大10人まで。同一求職者へのリクエストは1回のみです。
- 応募有効期間:リクエスト後7日間。ただし、この期間を過ぎても求職者はオンライン応募が可能です。
- 求職者マイページの開設が必須:リクエストを送るには、相手が「求職者マイページ」を開設している必要があります。
この機能を活用することで、単に応募を待つ受け身の状態から、企業が主体的に求職者に働きかけることができるようになります。メッセージの内容次第では求職者の興味を引きつけ、応募につながる可能性を大きく高めることが期待できます。
■機能上の注意点
直接リクエスト機能は、求職者がマイページを開設していない場合は利用できません。この場合、従来の方法でハローワークに依頼する必要があります。また、企業の管轄するハローワークによって取り扱いが異なる場合もあるため、詳細は事前に確認しておくとよいでしょう。
オンライン自主応募機能
「オンライン自主応募機能」は、求職者がハローワークを介さずに求人企業に直接応募できる仕組みです。この機能により、求職者は「求職者マイページ」を通じてオンラインで手軽に応募できるようになります。在職中の転職希望者やインターネットを活用する若年層にとって、ハローワークへ出向く必要がなく、スマートフォンを使って24時間いつでも応募できる利便性が魅力です。
■活用ポイント1.「オンライン自主応募可」の設定
求人票にこの機能を有効にする設定を行うことで、求職者が直接応募できる窓口を開くことができます。設定を忘れると応募が受け付けられないため、求人票作成時に必ず確認しましょう。
■活用ポイント2.登録メールアドレスと求人者マイページの定期的な確認
オンライン自主応募があると、登録しているメールアドレスに通知が届きます。通知を確認したら、求人者マイページにログインして応募内容を速やかに確認し対応してください。最低でも1日1回の確認を行い、応募者に迅速かつ丁寧に対応することで、企業への好印象を与えることができます。
■機能上の注意点
オンライン自主応募機能を利用して応募を受け付けた場合、ハローワークを介さない形式となるため、「特定求職者雇用開発助成金」や「トライアル雇用助成金」といった助成金制度の適用対象外となります。助成金を活用した雇用促進を考えている場合は、事前に適用条件を確認し、適切な対応を検討することが重要です。
また、オンラインでの自主応募は求職者が気軽に応募できる点がメリットである一方で、企業のニーズに合わない応募者が増える可能性も否めません。そのため、応募者を効率的に選考するためには事前に明確な選考基準を策定し、適切な体制を整える必要があるでしょう。
応募対応の遅れは、求職者が他の企業に流れるリスクを高める要因となります。応募があった際には、迅速な返信を心掛けることが求められます。丁寧な対応を行うことで、企業の印象を高め、求職者との良好な関係を構築していきましょう。
ハローワークを使いこなして採用活動を成功させよう
ハローワーク求人システムは、単なる求人申し込みの手段にとどまらず、企業の人材確保を支援する多彩な機能が備わっています。
しかし、このシステムに搭載された多くの機能が企業側に十分に知られておらず、その活用が限定的であることも事実です。これらの機能を使いこなすには、企業の採用担当者がシステムの仕組みや活用方法を十分に理解することが欠かせません。求職者目線で情報を充実させる工夫や、機能を活かしたタイムリーな更新が、採用成功の鍵となります
採用環境が厳しさを増す中で、「いい人材」や「欲しい人材」を確保するためには、各機能の仕組みやメリットを正しく理解し、自社の採用方針に応じて効果的に活用することが重要です。これらの機能を最大限に活用することで採用活動の効率化を図り、より多くの適切な人材との出会いが期待できるでしょう。
(参考)
弥報Onlineでは他にも「採用」をテーマにした記事を発信しています。
採用の記事を読む

この記事の著者
弥報編集部
弥生ユーザーを応援する「いちばん身近なビジネス情報メディア」

この記事の監修者
五十川 将史(ウエルズ社会保険労務士事務所 代表)
1977年、岐阜県生まれ。明治大学卒。大手食品スーパーの店長や民間企業での人事担当者、ハローワーク勤務を経て、独立。ハローワークを活用した採用支援を専門としている。商工会議所、労働局、社会保険労務士会などでの講演実績も多数あり、これまでの受講者は1万人を超える。著書に『中小企業のためのハローワーク採用完全マニュアル』(日本実業出版社)、『ハローワーク採用の絶対法則』(誠文堂新光社)などがある。